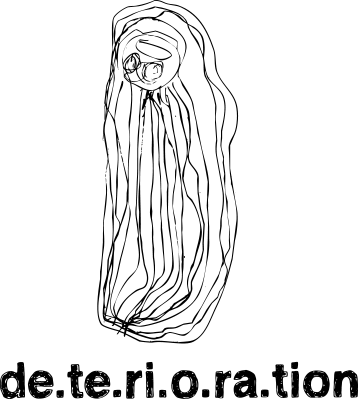NEWS
2018年8月9日
インタビュー/Naoya Takakuwa
Naoya Takakuwa”prologue”配信スタートとのことで、
メールインタビューをしました。
彼の創作の元になっている物事や今の世の中に対する考えなど語ってくれました。
とても興味深い内容になっています。
制限のないメディアなのでほぼ原文のまま載せています。
じっくりと読んでもらえたら嬉しいです。
インタビュアー・編集はAmi(Prince graves)です。
============================================================

Photo by Hanae Takakuwa
============================================================
-Ami(以下A)
今回のアルバム”Prologue”とても素晴らしかったです。
音楽性もさることながら、歌詞の世界観など個人的に引き込まれるものがありました。
コンセプトについては、自身のHP
Prologueのモノローグ
で語ってらっしゃるので、それを元に少し掘り下げてお話をお聞きしたいと思います。
よろしくお願いします。
最初の曲「Prologue」を聴いた時、すぐに映画”インヒアレントヴァイス”(ポール・トーマス・アンダーソン監督)のナレーションを思い出したのですが、影響を受けていますか?
-Naoya(以下N)
映画”インヒアレント・ヴァイス”を観た時に衝撃だったのがサウンドトラックとして使われているCANの”Vitamin C”だった。それで、僕はCANを聴き始め、サウンドや発声法を研究した。彼らの素晴らしいところは、まずダモ鈴木のヴォーカル。だって彼の歌はメロディを持っているのに、通常の歌のように前面に出てきていない。それが素晴らしいと思った。それからCANは”Soundtracks”というアルバムを作っているように、BGMとして聴ける音楽だった。それに彼らのライヴは素晴らしい。Youtubeで見たんだが、よく分からないアドリヴをし続けたりしているのがたまらなくよかった。
次に何と言ってもジョニー・グリーンウッドの音楽。僕はレディオ・ヘッドは聴かないが、グリーンウッドは天才だと思った。CANの流れを汲む形でサウンドトラックを作ってくれた。それで、インヒアレント・ヴァイスのサウンドトラックに収録されている”Spooks”という曲が肝だった。そこには映画の登場人物のナレーションが入っていて、それがグルーヴの一部を成していると思った。実際、それはポール・トーマス・アンダーソンの功績でもある。彼のインタヴューで読んだが、彼が受けた映画教育では、映画は映像によって語られなければならない、すなわちナレーションは使ってはいけないということだったらしい。それで、この映画までは一切ナレーションを使用することはなかった。だけど彼は、自身が好きな映画の中で、しばしばナレーションが使われていることを思い出したんだ。それで、ナレーションのアイディアを実行した。それは素晴らしいことだったと思う。彼はそもそも音楽と映像を組み合わせるセンスがあったし、そのやり方で、魅力的な音楽にナレーションを乗せることに成功した。
それで、そのアイディアを”Prologue”と”Epilogue”で使うことに決めた。歌詞を書き、妻に「LA訛りで」とお願いしてマイクに向けて喋ってもらった。これはあらかじめできていた曲をまとめあげる2曲になるだろうと思った。ナレーションでは、韻などの縛りがないため、自由に詩を書けたからだ。
また、トマス・ピンチョン著の原作「LAヴァイス」からも影響を受けている。それは、探偵物という枠組みで語られるパラノイア。そのアイディアは全く、ピンチョンからの借り物だと言っていい(ポール・オースターもかもしれない)。そして、様々な点と点がこじつけのように継ぎ合わされていく手法も。アルバム”Prologue”は一人の架空の探偵ナオヤ・タカクワを主人公とした小説になっている。歌物の曲は歌詞をできる限り切り詰めた物になっている。一曲一曲がテーマを持っているが、アルバムを通して、一つの大きなテーマになればいいと思った。先にも言ったようにPrologueとEpilogueがそれらの楽曲をまとめ上げる役割を果たしてくれたと思う。
-A
私はCANの”Vitanine C”が元々大好きだったのですが、この映画で流れた瞬間の格好良さは衝撃的でした。素晴らしい映画であり、サウンドトラックも完璧でしたね。あなたのアルバムの1曲目は奥様の声がとても美しく印象的で、一気に世界観に引き込まれます。”ナオヤタカクワ探偵事務所”の扉を叩いて、「まぁまず座って、一服やりなよ。」と声をかけられているような、そんな気持ちになりました。
さて、CANの名前が上がりましたが、他にインスパイアされたアーティストはいますか?普段はどのような音楽を聴いていますか?
-N
このアルバムに影響を与えた音楽でCANと双対を成しているのがピエロ・ピッチオーニというイタリア映画のサウンドトラックを作っていた人。コーエン兄弟監督の”ビッグ・リボウスキ”を見返していた時にピエロ・ピッチオーニが流れて、そのまま嵌っていった。その曲は”Traffic Boom”という曲で、映画内映画(というか登場人物が主演するポルノ・ムーヴィー)がブラウン管TVで流されるシーンのOPテーマ曲みたいなものとして使われていた。その映画内映画はフルハウスのオープニングのようにハイウェイを車が走るシーンから始まったんだったと思う。そのシーンが印象に残り続けたせいで、僕はビッグ・リボウスキのサウンドトラックを探したりした。不思議なことにこの「ビッグ・リボウスキ」という映画は非常に”インヒアレント・ヴァイス”に似通った映画で、主人公が探偵役となり、思わぬ方向に、思わぬ事件に巻き込まれ続けるという構成になっている。おまけに、ビッグ・リボウスキの”デュード”もインヒアレント・ヴァイスの”ドック”も変なあだ名から、ぼうぼうのヒゲ、体格、性格、マリファナ好きまで似通っている。とにかくその架空のポルノ・ムーヴィーの架空のサントラに僕の心は奪われた。
ピエロ・ピッチオーニの優れた点はロック・ビート、簡単なペンタトニックのロック・フレーズを用いつつもテンポのユルさ、無駄なまでの反復、そして歪まないギター・サウンドにより、完全にロックからロック気を抜くことに成功していることだ。その反復するフレーズ、微妙なところで展開する進行、それはある種の催眠状態を誘うことに気づいた。そういった点を参考にさせてもらった。僕はロック・ビートに飽き飽きしていたから。それで、ピエロ・ピッチオーニの簡易的で聴きやすく催眠的なトラックにCANの要素を組み合わせていくことが僕の目標となった。僕のアルバムの曲のうちいくつかはそう言った明確なゴールを持ってして作られた。だけど不思議なことに、CANやピエロ・ピッチオーニに出会う前に書いた曲”Horoscope”は既にそう言った構造を持っているし、彼らとの出会いは自分のあらかじめ持っていたヴィジョンを論理付けただけかもしれない。
現在聞いている音楽はジャズやフュージョンがほとんど。僕がジャズにはまるきっかけもピエロ・ピッチオーニにあって、彼は元々ジャズ畑の作曲家のためきっちりとしたジャズ作品やボサノヴァ作品もリリースしているし、そう言った関係からジャズを聴き始めた。と言ってもジャズを聴き始めたのはPrologue完成後である。僕はピッチオーニに嵌ったあと、彼が音楽を手掛けた映画を観たいと思ったが、日本語字幕付きで見られる当時のイタリア映画はとても限られている。それでも「流されて」という漂流物の映画を観ることができた。そのテーマ曲はボサノヴァ調だが、イタリア情緒も含んでいるように思えて大変良いのだが、行きつけのカフェでは度々その曲が流れる。その度ハッとして本から顔を上げ、「ピッチオーニだ」と呟いてしまう。
A-
前に皆で呑みに行った時に、あなたはBGMの有線から何気なく流れるジャズにも耳を傾けていましたね。
ピエロ・ピッチオーニは映画音楽、特にラウンジミュージックの印象が強かったのですが、”Traffic Boom”を聴いて、あなたの今作との共通点がとてもよく分かりました。
ロックのダイナミズムが排除された、反復するフレーズとゆるいビート。淡々とひたすら平静であるがゆえに周りの喧騒にかき消されてしまいそうな儚さもあるように感じました。
インヒアレントヴァイスの”ドク”、ビッグ・リボウスキの”デュード”にも共通する、「マイペースに生きているように見えるが、突然何かに巻き込まれてしまう。重大な何かが目の前で起きているのに遁世感がある。」という世の中との関わり方がキーワードでしょうか。
世の中といえば、あなたはアメリカで言うところのミレニアルズ(日本ではゆとり、さとり世代と言われたりしている)だと思うのですが、今この時代を生きている20代として、どのように感じていますか?音楽や創作にそれらは反映されていますか?
N-
はい、確かに我々はミレニアルズと呼ばれている世代ですね(笑)
僕の意見として言わせてもらうなら、ミレニアルズは生きる目標みたいなものを持っていない世代だと思う。同時に少子化の影響もあり、世代的マイノリティでもあると思う。考えてみてほしいが、目の前にリンゴとバナナを出されてどっちがいいですかと言われれば選ぶのは簡単だ。しかし全ての果物の木が植えてある果樹園に行き、「どれでも好きなのをとっていいよ、ただし一つだけね」と言われた時に何かを選ぶのは困難だ。
アルバイト先の主人にこう話されたことがある。「うちの息子がちょうどタカクワくんと同じ年だが、大学を卒業したはいいが、就職する気がない。それで困っているんだ。うちで、こないだ社員になった子もすぐやめちゃうし今の子達はみんなそうなのかね」と。そうだな、確かに僕も就職する気は無かったし、友人の多くも就職していない。それはまさに就職する必要がないからで、今はどこででもアルバイトとしての働き口があるし、それでお金に困ることはない。そもそも就職したってアルバイトに満たない初任給ぐらいしか貰えなかったりもするだろう。昔は、(簡単に言うとだが)家業を継ぐか働きに出るかの二択、それでことが済んだ。今は何もかもが簡易化されてはいるが、中身は複雑化し、我々は何のために生きているのかすらわからなくなる。そうした中、明確なゴールや目に見えるつながりをあたえてくれるTVゲーム機やSNSが我々の脳容量を萎縮させ、もはや常時マリファナ状態みたいなものだ。そういう意味で非常に彼ら(ドクやデュード)に非常に似通っているのが我々の世代だろう。「ミレニアル」がどういう意味かは知らないが、日本語で言うなら「ゆとり世代」というより「シラフでマリファナ世代」といったほうがいいかもしれない。
そして、そのことは僕の創作に非常に影響しているだろう。僕の書いた歌詞も今読み直せば、すべてそう言ったことを書いている気もする。それはつまり、世代的孤立、無思考状態への警鐘、死そのもの、そう言ったことだ。

Photo by Hanae Takakuwa
A-
「シラフでマリファナ世代」はかなり的を得ているような気がするし、面白い表現ですね(笑)
選択肢の多さが思考停止を招くのも、理解できます。確かあなたはスマートフォンを使っていないですよね。いつかの打ち合わせの時には文庫本を片手に現れ、それが”スローターハウス5(カート・ヴォネガット)”だったのがとても印象に残っています。
今は音楽も無数にあり、ジャンルやシーンという言葉は陳腐なものに感じますが、今あなたや私がいるとされている東京のインディシーンについてはどのように感じていますか?
親しくしているバンドは英語詞を選択していることが多いですが、そのあたりについても聞かせて下さい。
N-
まず、東京のインディー・シーン。これは死んでいる、と僕は感じている。なぜなら、このインディーシーンの源流となる2010年前後のアメリカのインディー・ロックが死んだからだ。もちろん「東京のインディー・シーン」のために音楽をやっている人間はいないし、皆それぞれ別のことを考えながら音楽をやっている。ただそれら時代の波から一つ外れメジャーな音とは違う音を鳴らしている者達、不器用な音楽が東京という街で一つの波を作っていたのだと思う。そしてそれは、主にイギリスとアメリカのインディー・ロックからの影響を多分に含んだものだった(僕の周りのインディー・シーンについて言っているため全ての東京の音楽に当てはまるわけではない)本場のインディー・ロックが死んだのはその実験性が模倣されるものとなり、もはや新しいものでもなんでもなくなってしまったことだ。しかしシーンが死んでもそれぞれのアーティストたちは生き続けているわけだ。僕が思うにこのインディー・シーンが面白かったのは、不器用さと変化、そして現在性だったと思う。けれどその全てが失われたと思う。でもこれはあくまで個人的実感としての話だし個々のバンドに当てはまるものでは一切ない。個々のバンドを見ているともちろん素晴らしいバンドが沢山いるわけだ。それでまた違った感触のシーンが新たに生まれるかもしれないし。
英語詞についてはDYGL、Cairophenomenons、Yüksen Buyers House、Wooman、Yuki Kikuchiらがそうだと思う。彼らがどういう意図で英語で歌詞を書いているのか知らない。DYGLの秋山は最初に曲を書いた時から英語で書いてたと言ってたきがする。僕の場合はちょっと違う。僕が英語で歌詞を書き始めたのは確か18歳ぐらいの時だったと思う。その前から曲は書いていたが、歌詞は日本語だった。日本語で歌詞を書く時の問題があり、英語と全く歌の感触が異なることだった。というのも海外のバンドの方が好きだったし、日本のバンドも好きだが、海外的サウンド・アプローチをしたいと思っていたから本当は英語の感触を出したかった。それでも最初のうちは日本語で英語の感触を出せないか奮闘していたが、うまいこといかない。それで、英語でも歌詞を書き始めた。そのせいで一時期は一つの曲に英語と日本語の歌詞がそれぞれあったし、音の響きを重視していたからそれぞれの歌詞の内容も全く違ったわけだ。その頃僕は生まれ育った石川県白山に住んでいたが、インターネットを通じて、現Teen RunningsのFriends、Moscow Clubなどを知っていたと思う。それで、英語で歌詞を書いても曲が聴かれる可能性はあるな、と思って英語で歌詞を書くことにした。
とにかく僕にとって大事だったのは言語的感触で、フレンチ・ポップはフランス語でやらないとフレンチ・ポップでないし、ボサノヴァはポルトガル語でないと雰囲気がでない、そう言ったことだ。今回のアルバムではジャパニーズ・イングリッシュに寄り目の発音で歌っている。なぜなら、CANはジャパニーズ・イングリッシュでなければやはりCANではないからだ。かといって僕が完全にCANをコピーすることが目的だったってわけじゃないけれど。だけどジャパニーズ・イングリッシュで歌うことは僕が日本人であるというルーツも示すことができるし、なかなかいいなとは思ったよ。
A-
同世代で活動しているバンドがたくさんいるのは、あまりそういうところに居なかった私から見るととても羨ましいことです。
シーンとかではなくても、個々でスタイルを確立していて、お互いに磨きあっている感じがしますね。
英語詞で作ることに関して、よく私も聞かれるので考えていましたが「英語の感触」を出したいというのは同感です。自分が作る音楽に日本語の歌詞が全く浮かばないんです。
最後になりますが、私は今回のアルバム”Prologue”は、あなたの音楽人生においてまだ「序章」だということを意味しているのかなと、解釈しました。実際にはどうでしょうか?これからの展望、やってみたいことなどあれば教えてください。
N-
実際にその通りで、”Prologue”というタイトルはこのアルバムがほんの始まりに過ぎないということを表している。それこそ分厚いミステリー・ノヴェルの最初の数ページぐらい。それと同時に我々の人生についてでもある。つまり一人の人間の生まれてから死ぬまで、それは大きな一つの物語に思えるかもしれないけれど、大きな物語のほんの一部分に過ぎないということだ。それがまさにアルバム最後の曲、”Epilogue”にて語っていることだ。それはどういうことかというと例えば、アリの行動を観察すると彼らは集団で一つの生物のような動きをしていることがわかる。蟻の巣の構造だって一つの生物の内臓みたいに見える。彼らは一匹一匹が「個」であるが、それと同時により大きな個の「部分」でもある。それと同じように我々人間は、そして人間社会の構造は、そして文化は、集団であるがゆえに存在、確立しており、自分一人では人間というものすら成り立たないのだ。特に現代社会においては、我々は一個人としての意識が強くなり、集団としてでなく一人ひとりの人間が全く別の生物であるかのように感じている。そういった現代社会において、自分以外の別の人間の人生を想像してみることは重要だと思った。無数の人間の生き方が織り合わさって作られているのが社会なのだから。我々は他人が何か思いがけない行動をとったりした時、それについて真剣に考えてみなければならない。なぜなら、その他人も自分と同じ構造を持った一人の人間であるからだ。
今回のアルバムではほんの一つのアイディアを提示したに過ぎないので、また別なこと、新しいものを作っていきたい。それは音楽でも詩でも映画でも構わないと思う。どれでも結局は同じことだからだ。沢山のレコーディングをし、沢山のライブをする。そういうことができればいい。できれば80歳ぐらいまでは。
A-
たとえそれが音楽という形じゃないとしても、今後もあなたの作品や活動を楽しみにしています。
ありがとうございました。
2018.8月