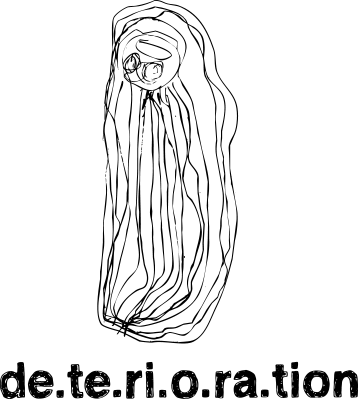MAGAZINE
ナオヤ・タカクワの日記〜2020.07.31-08.06
7月31日(金)
もう7月も終わるというのに、梅雨が続いている。朝起きて肌寒いのには首をかしげる。いくらなんでも8月に入るって天気ではない。空は常に曇っている。天気予報で降水確率が10%であったとしても傘を持って出かける。どうせ降るに決まっているからだ。今年の梅雨は僕に天気予報への不信感を強めさせた。大体、天気予報はフィクションだということに今まで気づかなかった僕が馬鹿だったのだ。
皆、知っての通り、天気予報はフィクションである。それは朝の情報番組(と言えるか怪しいTV番組群)の中で星座占いと大体セットで放送される。そもそも、星座占いが正しいかどうか、ということはここでは問題ではない。あくまでもそれは、事実ではなくフィクションであり、一種の儀式でしかないのだ。我々は毎朝教会へ行き、祈る代わりに、天気予報や星座占いを見て祈る。我々が祈るのは神に対してではない。別に天気に祈るわけでも、星座に祈るわけでもないし、天気予報士や占い師に祈るわけでもない。我々には祈る対象が欠落しており、それはスクリーンという代用品を持って示される。神の教えがイエス・キリストやブッダを媒介して人々に伝わったように。ただしいくらスクリーンに対して祈ろうとも、その向こう側には神も仏も存在していないのだ。
8月1日(土)
先日購入したウディ・アレンについての本を読んでいる。1987年に出版された本だ。少しカビ臭いが、中身はまともだった。87年の日本で書かれた文章は少し古いが、少し新しい。ちょうど、平成に入る手前という時期だ。皆、平成なんて時代は知らない。勿論令和も。永遠に昭和が続くのではないかと思われた時期である。僕はまだ全く生まれる気配すらなかった頃だ。本は人間より長生きするから、死を感じさせない分人間より付き合いやすい。それでも様々な形で彼らも死を迎える。死ななかった本や死ねなかった本があるが、死んでいった本の方がずっと多い。僕は死を感じさせる本は人間より苦手だ。
87年ではウディ・アレン映画のVHSやベータが1万5千円ぐらいだった。当時の人々は1万5千円ぐらいでVHSを買うのが当たり前だったのかもしれない。我々は毎月千円ほどで、300本ぐらいの映画を観ることができる。しかし勿論そこに値段と同じ分の質的な差は存在しない。ショウ・ビズは死んでいくのかもしれなかった。そして死ぬというのは元ある場所に戻っていくことだ。音楽も映画もファッションもレストランもみんな元ある場所に戻っていこうとしているのかもしれない。我々はそれらの元々の姿を覚えていないだけなのだ。ある文化が衰退していくこと、それは実は衰退ではなく、あるべき姿に戻っていくということ。毎日死ぬ気でギターの速いフレーズを練習したり、寝る間を惜しんで同じVHSを30回も観たり、そんなことは彼らのあるべき姿では無かったのだ。我々は資本主義とともに大量のものを消費し、消費するためのものを生産し、生産するために、そして消費するために働き、また消費することを繰り返しすぎたのだ。意外と資本主義の終わりはすぐそこで、ブルジョワジーや1%の金持ち達は時代に取り残された過去の昭和的遺物でしかないのかもしれない。
8月2日(日)
憂いていた梅雨は明け、夏らしきものが始まり、洗濯物の乾きは良くなった。僕の持っているコインランドリー用のプリペイドカードは残額1400円を残したまま用済みになってしまった。そういえば、以前壊した携帯電話の中にも、5千円分のSuicaチャージが残っていた。僕がこうして食べ残しみたいに置いていった金は、誰がどうやって、何処へ運んでいくのだろう。多くの食べ残しがそうであるように、ゴミ箱に捨てられ焼却処分されるのかもしれない。または、誰の仕業ともしれない風みたいなものに吹かれて、海に浮かんでいるのかもしれない。やがてそれらは海岸に打ち上げられて、不要となった金の死体置き場みたいなものが出来上がるのかもしれない。それを吸い取る掃除機みたいなものが作れれば僕は大金持ちにだってなれるというのに。
8月3日(月)
朝のアラームを本来あるべき時間にセットし忘れたおかげで僕は寝坊した。「もう8時を10分も過ぎてるわ!」こんこんと眠り続けていたのを妻が起こした。5秒で支度をしたが、間に合うはずはなかった。僕は空中にある一点を、そこにあったはずの何かを探し求めるように、5分ほどじっと見つめた。上から、下から、右から、左から。僕は様々な方向へ身体をくねらせながら、それを探し求めたが何も見つかることはなかった。結局のところ、そうしたって何も見つからないってことは最初からきちんと僕にだってわかっていたのだ。ただわかっていないふりをしていただけだ。それでも、わかっていないふりをしているだけだとしても、何かの助けにはなった。
妻に感謝しながら家を出た。少なくとも彼女のおかげで、1時間や2時間も遅刻してしまうことは防ぐことができたのだ。それでも僕は時々思う。何処の誰が毎日6時半に目を覚ますことができるんだ?しかし、僕の祖母は毎日きっかり5時半には目を覚ましていたのも事実だ。僕はもっと寝ればいいのにと思った。彼女は毎日ちゃんと5時半に起きていながら、それによって何かを手に入れているようには見えなかった。少なくとも、どちらかといえば少しずつ何かを失っていくように見えた。それは神聖で美しいと思う。だけど僕は神聖で美しくなんてなりたくはないのだ。
僕は玄関で昨日買った靴に足を滑りこませた。2つ向こうの部屋から「いってらっしゃい!」という声が聞こえた(妻の尊厳のために言うが、実際には彼女は玄関まで来てくれて口づけをしてくれた。それにも関わらず、僕はそれを排除したのは文章のなめらかさを保つためだ。ある文章の中では文章そのものが王様であり、事実であるかどうかというファクトチェックは二の次なのである。そして僕はファクトチェックを甘く甘く設定しておくことで文章のなめらかさを保っている。少なくともその気でいる。そしてこのカッコ書きの文も全て文章のなめらかさを保つために書かれているのだ。それが、絹ごし豆腐と木綿豆腐の違いである。僕の文章はなめらかさという点では絹ごし的だが、木綿的な乱暴さも併せ持っていると思う。だけど実際にあれらの豆腐が作られるときに絹や木綿で漉されているのだろうか。もしそうだとするなら、試しにユニクロのジーンズで濾した豆腐なんてものも作ってみるのも悪くないんじゃないかと、僕は思うわけである。藍染デニム濾し豆腐1丁2千円ってのを、どうか豆腐業界のみなさま、この文章を読んでいらしたら商品化してくだされば僕は少しの欲望を叶えることができ、晴れた気持ちでこの迫り来る永遠のような夏をなんとか過ごしていけるかもしれない)
僕はドアを開け、蝉の劈くような、断末魔のような叫び声に鼓膜を揺さぶられながら、今日もまた、シャツの袖を左右3回ずつ折ってから、藍色のポリエステル製のマスクを口につけ、何処かへ向かおうとする(そのマスクは裏表が反対だったことに数時間後の僕は気づくことになる。そして反射的にマスクを裏返してつけた。僕の口に入らないようにマスク表面でブロックされていた飛沫類があったとしたら、それは全て僕の口や鼻と密着してきた。マスクの中でなんともいえない居心地の悪さを感じながら一日を過ごした。まあ、こんな日も悪くないだろう。少なくとも蝉よりましかもしれない)
8月4日(火)
ブコウスキーの本がポケットに入っていれば、我々はかろうじて自我を保つことができる。ブコウスキーのいいところは、仕事を見つけては二週間でやめるのを20回ぐらい繰り返すところだ。それに、女を見つけては二ヶ月ほどで別れることを何度も繰り返すことだ。それは、絶望の先に希望があるということを表しているわけではない。絶望の先にも絶望しかないことを提示して見せ、アメリカン・ドリームの嘘、社会的成功のまがい物感を暴き出すことだ。そして、「努力は報われる」という神話をショットガンでバラバラに吹き飛ばすことだ。そもそも努力なんてしない、というところが重要だ。それでも書き続けることは、何の意味もないことなのかもしれないけど、少なくとも何かの役にはたっている。
8月5日(水)
晴れた日だ。晴れた日も一週間も続くと、曇って欲しくなる。人間はそこにはないものを求める生き物だ。冷蔵庫がなければ冷蔵庫を欲しがるし、履くものがなければ靴を欲しがる。他の誰かがそれを持っていれば尚更だ。こうして起きる「くだらない買い物」の数々を資本主義という化け物が飲み込んでいく。その資本主義が美しいものだというのもまた事実だ。美しいものは儚い。一週間で散ってしまう桜の花、皆既日食、すぐに汚してしまうことがわかっている新品の白いシャツ、早死にした音楽家、アルデンテのスパゲティ。資本主義のことを美しいと思うのは、それの終焉の姿が見えるからかもしれない。崩壊しかけているものは何よりも美しい。ピサの斜塔や両腕を失ったヴィーナスのように。
僕は無駄な買い物に勤しむ。資金を持ち、ブックオフへ向かって誰かの捨てた何かを手に入れることで、資本主義者として、資本主義の世界を生き延びようとしている。バミューダパンツと帽子を手にとり、鏡の前で合わせてみる。くたびれた札束を身にまとった姿は滑稽で、思わず笑いがこみ上げてきてしまう。試着室にて、腹を抱えて、床に這いつくばって、笑ってしまった。
人々は皆滑稽で美しい。しかしその美しさが滑稽さから来ていることを知らないと、我々はその本質を見逃してしまう。滑稽であることが正義であるのは、コメディの世界だけではない。我々は滑稽であればあるほど美しくなっていくのだ。生肉のドレスを着たレディ・ガガがあんなに美しいのは、女物の服を着てステージに上がるカート・コバーンがあんなに美しいのは、なぜかということはそれを考えてみれば不思議なものではないのだ。
8月6日(木)
イソジンがCVID-19に効くかどうか。そんな論争が、別に耳にもしたくないものが、TVを持っていなくても、新聞をとっていなくても、ラジオを聴いていなくても、耳に入ってくる。聞きたくないものが耳に入ってくるので、耳掃除は年に一度と決めた。あまりに耳がいいと、余計なことまで、知らなくていいことさえ、容易に僕の脳内のデータベースに入ってきて、PCとは違い精度が低く容量の少ないハードディスクをすぐに満杯にしてしまう。そのおかげで酒が進み、翌朝、覚えていなければいけないことすら覚えていられないという不条理が発生し、ただでさえ困難な生きるという行為をそれ以上に難しくする。僕は電気屋に向かった。容量がいっぱいになった僕の記憶の倉庫に少し容量の大きいハードディスクを設置するためだ。
電気屋の店員はとても丁寧だった。僕が求める品物探しを一緒に手伝ってくれた。彼らは僕が話しかけさえしていないのに、「何かお探しですか?」半分オートマティック、半分本気で訊いてくるのだ。そして口元には半分がオートマティックで半分が憎しみやら、苦しみやら、早く帰宅してビールが飲みたいという欲望などに彩られた素晴らしい笑みが浮かべられている。僕は一種の超能力、とまではいえないが一種の特技を持っており、それによりその笑みのうちの一本一本の皺に意味を見出すことができる。昨日食べた夕飯にニンニクが効きすぎていたかな、とか。「昨日食べた夕飯にニンニクが効きすぎていたかな」の笑みは口唇の真ん中からみて5センチ右、そこから3センチ上に行ったところから右下に向かって45度の角度で1.5ミリの長さである。今日の店員は効きすぎたクーラーのせいで紫色の唇をしており、それを悟られまいとするための皺(これはなかなかレアな皺だ)が小鼻から右に4センチのところに発生していた。
勿論、彼は僕がハードディスクを探していることを知っていた。僕のハードディスクが圧迫されていることも。ハードディスクのコーナーをこれほど真剣にのぞいている客は他にはいないからだ。一種の好奇心さえあったに違いない。彼は半分の恐れと半分の興味を持っていた。
「どんな商品をお探しですか?」と彼は訊いてきた。僕はできるだけたくさん入るのがいいと答えた。今のでは不十分なのだと。できれば交換ではなく増設をしたいとも答えた。僕はこう見えてノスタルジックな感性を持っているので過去の思い出や、それに付随する匂い、触覚、興奮、恥辱的な感覚、名も無い感覚、絶望的な感覚、それらの全部を愛していたし、失いたくはなかったのだ。
しかし、店員はその意味では冷徹だった。
「うちではそれほど容量の多いのは置いてません。だけどその分高性能ですよ。AIによって記憶がそれぞれ整理されて、引き出しの中にきちんと畳んでしまってくれるんです。それにそれぞれの引き出しにはきちんと付箋がついていて、何の記憶なのか、何のための記憶なのか、必要か必要でないかを識別するんです。それで必要ないと判断された記憶はしっかりと処理されます。処理された記憶はすごく小さくなります。だからつまり、容量の大きさはそれほど重要ではない、というのが今の主流なんですよ。少し見てみてもいいですか?」
彼は僕の後頭部の二箇所を抑え、慣れた手つきでぱかっと開いた。
「うーん、やっぱりそうか。あなたの脳味噌を圧迫しているのはほとんどがいらない記憶ばかりですよ」
そして彼はスポイトを使って緑色の液体を僕の頭の内部に満遍なく垂らした。少し沁みる感覚がした。最近はどこもこうだ。勝手に人の身体をいじくりまわしていいと思ってるんだ。
「どうです? この色が紫色に変わっているところがあるでしょう。この紫色の部分はあなたに本当は必要のない部分なんです。みていてください。3分もすれば結果が見られますよ」
合わせ鏡を器用に使って、僕の脳内を僕に見せてきた。あまり気分のいいものではなかったし、少し吐き気を催したが、怖いもの見たさというのだろうか。僕は3分間待つことにした。
3分後、僕の頭の中のほとんどすべての部分が紫色に変わっていた。「それで、どうします?容量も一番いいのだと1テラバイト。これで税抜き4万9千円です」僕は何も買わずに店を出ることにした。5万円を払って、脳内をコンピュータに掃除や片付けをさせるなんて馬鹿げているように思えたからだ。それくらいのことは自分でやりたかったし、必要かどうかは僕が決めるべきだと思う。店を出ると、シャツが肌に張り付いてきた。僕の目頭は熱くなってきて、視界がぼんやりと、チカチカした。夏が始まったところだった。路上にホームレスたちがいた。段ボールに寝転がって心地よさそうだった。僕の抱えている悩みのうちのほとんどすべては彼らには関係ないだろうなと思った。僕は銀行に行って5万円を受け取り、電気屋に引き返した。
続く
前回までの日記
執筆者:Naoya Takakuwa / ナオヤ・タカクワ
1992年生まれ、石川県出身。東京を拠点に活動するミュージシャン、作曲家。前身バンド、 Batman Winksとしての活動を経て、2017年、 ソロ名義での活動を開始。2018年にアルバムLP『Prologue』をde.ta.ri.o.ra.tionより発表。現在は即興演奏を中心に活動中。2019年には葛飾北斎からインスパイアされた即興ジャズ7曲入りCDーR『印象 / Impression』付きの書籍『バナナ・コーストで何が釣れるか』がDeterio Liberより刊行された。