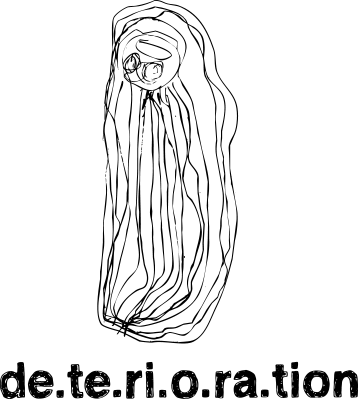MAGAZINE
ナオヤ・タカクワの日記〜2020.09.18-09.24
「音楽家ナオヤ・タカクワによる日常の批評的分析」
9月18日(金)
僕の知らない別の世界に来てしまったみたいだ。何かがいつもと違うことに気づく。無は無として存在するはずなのに、無が存在していないのだ。僕がそれを感じ取ったのはカップ焼きそばに湯を注いだ時だった。通常は、カップ焼きそばに湯を注ぐと得体の知れない虚無感に襲われる。僕はいわばその虚無を得るためにカップ焼きそばを食べるのだ。
カップ焼きそばに湯を注ぐ時の虚無感について少し解説したいと思う。カップ麺が虚無感を生み出すのには、大いにメディア的イメージが関係していることは間違いない。数多のテレビドラマの中で、カップ麺は孤独と荒んだ生活を象徴してきた。独り身、無職、貧乏、不摂生、それらのイメージを表象する道具として、手っ取り早く、安価であり、湯を注ぐ行為は儀式的で艶めいて見えるというその性格上、テレビドラマ現場の小道具係たちに大受けの商品としてあらゆるテレビ局で引っ張りだこになっていたのだ。特に、煙草の有害性が科学的に立証されて煙草のテレビ露出が制限され始めた1990年代以降、その傾向は顕著になった。今までは煙草が演じていた役割をカップ麺が代替可能だということに、数多のスクリーンテストの結果、プロデューサーたちが気づいたのだ。
これからは煙草に代わって、カップ麺がワイルドなイメージ、やさぐれたクールさ、アウトロー感を演出する汎用性の高い道具として世間を席巻するであろうことに優秀なプロデューサーたちは気づいていた。特にカップ麺の潜在的特色、煙草の「けむり」の代わりになる「湯気」を発することと、そのカメラ写りのよさが好意的に迎えられた。おまけに当時、インテリの代名詞であった眼鏡をかけた人物がカップ麺をすすると、眼鏡自体が曇るということ、そして撮影用カメラのレンズを曇らせる技術により、視聴者が、まるでドラマの登場人物と一体となったような臨場感と共感を得られることも判明した。かくしてカップ麺はエンタメ業界の華としての地位を確立したのだ。
以上の説明により、メディアがもたらしたカップ麺の虚無的イメージと、それがいかにして煙草がスクリーン上で占めていた地位をかっさらったのか、ご理解いただけたと思う。しかしそれにも増して、カップ麺には虚無感を煽る別の、本質的な特徴があったのだ。そして、それは「カップに湯を注いだ後3分待つ」という行為である。
これから3分後の未来に何が起こるのかを知っていながら、それをただ待ち続けるという行為。それはある種、死に似ていると思うのは僕だけだろうか。それに、その3分間、その他の多くの料理と違って、手を動かすこともなければ、吹きこぼれないか鍋を見張っておく必要すらない。僕たちにできるのはきっちり3分間待つことだけだ。そしてその間、3分後に起こるであろう舌に感じる塩分過多の痺れを想像しないわけにはいかないのだ。もちろんそうした想像によって僕たちの口内は涎で濡れ渡る。口内における水分の分泌はパブロフの犬を想起させるのには十分だし、その他の犬的イメージ……文字通り餌を前にして「待て」の命令を遵守する犬たちのことが鮮明に脳裏に浮かび上がる。犬たちも「待て」を食らっている間、死の予行演習をしているのかもしれない。そしてもちろん、死は虚無である。
ところで、僕が今日虚無を感じることができなかったのは何故なのだろうか。虚無の不在の中では何もかもが満たされている。3分間の待ち時間すら僕は満たされていた。虚無の不在は僕に幸福に似た何かを残し、しかしそれは粘度の高いマカロンを2個続けて食べた時のような甘ったるさで、やはりあの虚無が恋しくなるのだ。一番有力な説は今日の僕自身が虚無であるから、というものだ。虚無と虚無の組み合わせは、マイナス同士の掛け算と同じように打ち消しあうのだ。そう、考えても見れば、カップ麺のための湯を沸かす手前までは僕は虚無でいっぱいだったのだ。その虚無の原因はあまりにもプライヴェートな事柄であるので、ここに記すことはできない。また別の機会があれば、僕のこのささやかな秘密を打ち明けたいと思うのだが。
9月20日(日)
ベッドから一歩も出ることができない日というものが、正常な人間であれば1ヶ月に1回はあるものだと思うが、今日がその日に当たる。このような日にはベッドから出ないことが良い結果を生むことは僕の経験則上100%の確率で保証できる。それでも、正直に打ち明けてしまえば、「ベッドから一歩も出ることができない日」であっても「ベッドから一歩は出る」ものだ。それは現在僕がベッドから出てそのすぐ隣にあるデスクの前に座って、パソコンへ向かっていることからも分かるだろう。
ワーカホリックに陥ることにより半ば強制的な幻覚状態に身を置くことによってしか、ベッドから抜け出す術はない。そのことは毎日仕事のために早起きしてベッドを抜け出す人たちであっても、休日には午後1時を過ぎるまではベッドから抜け出そうとしないことが証明している。我々現代人は潜在的ワーカホリックに陥っているというのが僕の持論であるが、非ワーカホリック的生き方、すなわち反社会的生活、もしくは野生動物的行動様式を備える非現代的生き方においては、腹が減る、小便がしたい、などの欲求がスイッチとしての役割を果たし、目を開けるというシステムが身体構造の中に組み込まれているのだと考えられる。そのシステムが人々の生活様式から強制的に排除される人間社会においては、我々は全て病的な幻覚の中に身をおいていることになるのだ。
9月23日(水)
午後3時を過ぎた後に昼食をとる際には、それまで潜在的、そして無意識的に増殖していた空腹感の爆発により適当な安価の弁当で済ませることは物理学上不可能となる。そんなわけで、財布の中に入っているなけなしの小銭たちをチェックしつつ、行きつけの会員制高級ファーストフード店、やよい軒へと向かうことにした。勿論、注文する定食は揚げ物メニューの中から選ぶ。揚げ物はその油分と塩分により僕の中に溜まって、渦巻いている食欲に火をつけ、その暴発により白飯を通常の3倍食べることができるというロジカルな利点を持っているのだ。ハイスペックな券売機のタッチパネルを駆使し(そしていささかタッチパネル上の雑菌やウイルスを気にしつつ)メニューを物色する。唐揚げ7個の定食と迷ったが、チキン南蛮とエビフライ2本のセットを注文することにした。
チキン南蛮にもエビフライにも同じタルタルソースがかけられている。タルタルソースは乾き、黄色く変色していて、それは高級店ならではの美学を感じさせる。そう、ある種の料理は美術品にも匹敵するのだ。あられもないような姿で鎮座するエビと鶏もも肉にたっぷりとした半固形、半液体のソースがかかっている姿はMOMA美術館に飾れば新たなポストモダン・アートとして注目を浴びることは間違いなかっただろうが、今まで美術家たちがそれをサボってきたことにより、すでにただのポスト・モダンに価値はないという時代が到来してしまい、やよい軒の定食は美術的過小評価をされることになった。ディキシーランドジャズを愛する懐古趣味な僕にとっては、2020年のアートとしてはいささかレトロであるとは言え、この素晴らしい定食=美術品を美術館へと持ち出すのは自分の役割であるように思えた。
とは言え、僕は胃袋の中で渦巻く強固な新型台風「ハングリー」を制御することができない。風は吹きすさび、雨は雪崩のように降り続け、それらの自然現象は神の振る舞いにも似ており、それを抑えるための生贄を僕の体は必要としていた。一方では生贄に捧げるものがあり、一方では恩恵を受けるものがいる。それが、結局は資本主義の構造なのだから仕方がないだろう。僕は現代美術史に一つのターニング・ポイントを残すことになったかもしれない稀代のポスト・モダン定食を神に捧げることによって、嵐のような空腹が次第に鎮まっていくのを感じた。罪の意識が芽生えるのを感じないわけには行かなかったが、その反対側に位置している快楽が満たされていくのを我慢することはできなかった。そして満足感とともに、美術や芸術や音楽のことなんかはどうでもよくなって、ぱんぱんに膨れ上がった腹を締め付けるベルトをワンサイズ下げて、これからやってくる新たな台風「スリーピィ」に向けて臨戦態勢の準備を始める。
続く
前回までの日記
執筆者:Naoya Takakuwa / ナオヤ・タカクワ
1992年生まれ、石川県出身。東京を拠点に活動するミュージシャン、作曲家。前身バンド、 Batman Winksとしての活動を経て、2017年、 ソロ名義での活動を開始。2018年にアルバムLP『Prologue』をde.ta.ri.o.ra.tionより発表。現在は即興演奏を中心に活動中。2019年には葛飾北斎からインスパイアされた即興ジャズ7曲入りCDーR『印象 / Impression』付きの書籍『バナナ・コーストで何が釣れるか』がDeterio Liberより刊行された。