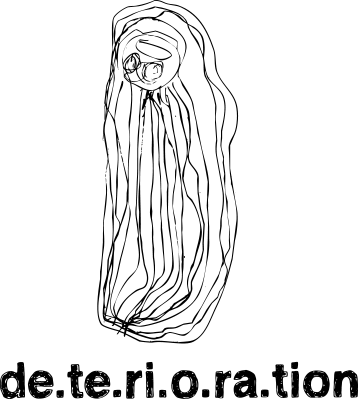MAGAZINE
「愛おしき、アリエル・ピンク」音楽家ナオヤ・タカクワによる日常の批評的分析〜第六回
緩やかで激しい年末と年始を過ごした。それらの全てが終わったあと緊急事態宣言が発令され、我々は様々な情報に惑わされ、飢え、求め、妬み、食すようになった。陰謀論が巻き起こり、右は左になり、左は右になった。上が下になり、下が上であるのが常識となった。その昨年から続いて第二回目の忌まわしき号令の前日にアメリカ合衆国では議事堂が襲撃される事件が起こった。そして僕はそれに関連するひとつのニュースを目にすることになる。それは僕にとってノスタルジックな出来事であり、音楽聴取の趣味と意義を一転して変えさせた。
アリエル・ピンクことアリエル・マーカス・ローゼンバーグが1月6日、ドナルド・トランプ支持集会に参加していたことが明らかとなった。その集会が元となりアメリカ連邦議会の議事堂への襲撃が行われた。1月9日、彼の所属レーベルメキシカン・サマーはアリエル・ピンクの解雇を言い渡した。アリエル・マーカス・ローゼンバーグは「平和的に大統領への支持を表明した」を語っており、議事堂への襲撃には参加していないと言っている。
このニュースが僕にノスタルジックな気分を思い起こさせたのは、アリエル・ピンクのカルト性、子供のまま大人になってしまったおじさん感、どこまでがジョークでどこからが本気なのかわからない掴めなさ、そしてレトロでノスタルジックなサウンドを再現する現実逃避の姿が鮮やかに浮かび上がってきたからだ。
数年前まで僕はアメリカンインディー音楽を愛聴していて、その中でもアリエル・ピンクは特別な存在だった。彼の金髪で長髪で女装趣味でやけくそな歌い方はカート・コバーンを思わせたし、どう見積もってもカート・コバーンよりオタク的、ダサくて陰気、コミュニケーション能力の欠如、歌の下手さ、不器用さ、それらが少なくともポップチャートで受け入れられていることは僕に安堵と希望をもたらした。オタクがヒーローに変身したのがサム・ライミ版『スパイダーマン』だとして、アリエル・ピンクの登場が提示したヒーロー像はオタクがオタクのままでいて、尚且つ時代がオタクに追いついてくるという希望だった。
アリエル・ピンクス・ホーンテッド・グラフィティ名義のアルバム『ビフォー・トゥデイ』が発売されたのは2010年のことで、それは新たな時代の始まりを思わせた。その後のアリエルの様々な活動は僕の希望を少しずつ増強していった。チューイングガムを風船型にぷくっと膨らませるようにして、彼の息吹が僕の自意識に潜り込み次第に膨らんでいくのを肌で感じたのだ。
例えば、2011年に野外フェス「コーチェラ」で行われたパフォーマンスではアリエルは一切歌うことを拒否した。それをユーチューブに上がっている画質の悪い携帯カメラ撮影の映像で楽しんでいた僕は、そのボイコットが何を意味するのかわからなかったけれどとにかくそれがクールだということはわかった。歌を歌うべき場面で、あえて歌わないということは何か大きなものへの抵抗に思えたし、真面目な他アーティストたちの振る舞いは予定調和的であり、消費のための音楽を提供するお披露目会的パフォーマンスは僕のことを常に萎えさせたからだ。予定調和を崩すもの、それはハプニングを意味した。僕はとにかくハプニングを求めていた。思春期特有の慢性的な鬱傾向に苦しむ自分を変えられるのは、ハプニングでしかあり得ないとも思った。意図せぬ何かが世間を変えてくれることを信じていた。
僕はその後数年に渡ってアリエル・ピンクを聴き続けてきた。過去の悪質な音質の宅録音源にも手を出していったし、『ビフォー・トゥデイ』に続く2012年の『マチュア・シームズ』2014年の『ポン・ポン』を僕はすり切れるまで聴いた。実際はアイフォーンで聴いていたので何かが物質的に擦り切れてしまうということはなかったが、聴きすぎて鼓膜の奥から脳に染み込んだ音波振動が少しずつ脳の一部をかすめとっていくような気分になるまで聴いた。『ポン・ポン』発売当時が僕のアリエル・ピンク崇拝のピークだった。発売前に試聴可能だった数曲を永遠にリピートして聴きながら発売日を待ったものだ。
彼の音楽に現れていたのは幼少期にラジオから流れていた懐かしい音楽のようなもの。そして電波のノイズや擦り切れたレコードのノイズとともに音楽の記憶が長い時間を経て、記憶そのものに発生したノイズごと再現しようとしているような印象を僕に与えた。音楽そのものをゼロから作り出すのではなく記憶のなかに流れている音楽を再現しようとするやり方は誰にとっても新鮮だった。音量レベルが限界を超えたために発生したノイズ――言うまでもなくロックンロールの始まりはゲインを上げすぎたエレキギターの音である――それは子宮の中で聴いていた音、夢の中で流れている音楽、アナログテレビの砂嵐に似ていて、それは安心と興奮とを同時に人々の心に呼び起こさせた。
夢の中で流れているような抽象的でとりとめがなく、不安で、心地よいサウンドは後のチルウェイブに影響を与えたし、部屋の中で一人で音楽を作ると言う姿勢もまたしかりだった。部屋の中で作られたということが子宮性を付与していたのかもしれなかった。またその孤独は不安を同時に残したのかもしれなかった。とにかく「宅録」という今まで世間に見向きもされなかった音楽にスポットライトを当ててくれたのだ。
********************************
今回の出来事は僕にとって別にショックではないし、アリエルはどこまでも通常運転だなと思わせてくれた。しかしそれと同時に世間が変化してきているということも僕に知らせることになった。彼の活動は全て破壊的な諧謔に満ちている。ステージではショルダーバッグを肩にかけたまま歌う。金品を盗られないためだと言う。またフェスに出演した際には一曲丸々歌を歌わなかったこともあった。それが彼の持ち味であり、全て意図的だとも言える。そのアクの強さは時折悪い方向へシフトしてしまうし(というか大概のことが悪い方向へしか向かっていないのだが)アルバム『ビフォー・トゥデイ』以降のヒットは予想外だった、と言える。だけどそれは起こったのだし、それ以降も彼は彼のままだった。
陰謀論的なものを支持することは、彼の諧謔のひとつだったかもしれないしそうではないかもしれない。これまでの彼の行動の全てだってジョークだったのかもしれないし本気だったのかもしれない。それは誰にもわからない。少なくともアリエルの、全てを煙に巻くような言動から推察することは非常に難しい。彼自身の姿は彼の音楽と同様濃い霧で覆われていて本当の形を見ることができないのだ。
2012年にアリエル・ピンクとR・スティーヴィー・ムーアが合作で出したレコード『クー・クラックス・グラム』はジョークだったのか、そうでは無かったのか。クー・クラックス・クランとグラム・ロックを両方本気で支持していたのかもしれない。白人至上主義的思考を持っているのかもしれない。それでも彼の父親はユダヤ人であるし、そのことから我々はまた煙に巻かれてしまうわけだ。
コロナ時代が長引くにつれ世の中には陰謀論がはびこり、真実は濃霧のなかにあるように知り難くなってきた。人々は何に対してでも文句を言うし、その言動に対して責任を取る必要はなくなった。世間そのものがアリエル・ピンク化してきたのだ。一方で「正しいこと」が規定されその「正しいこと」から道を外したものはすぐに糾弾されるようになってきた。それは特に有名人に対して行われる。圧倒的多数の目出し帽を被った匿名ユーザーたちに対して、有名人たちは紙マスクすら付けずにで顔面を全て露出させているからだ。マスクなしの人たちが批判、攻撃されるという構造はまさに、コロナ禍の我々の生活そのものみたいだ。
アリエル・ピンクの2007年のアルバム『スケアード・フェイマス』は現在のこの状況を予言していたのかもしれない。「怖がる有名人たち」というこのアルバムはこれまでで僕が最も聴いたアルバムのひとつだ。この病いには特効薬もワクチンもない。僕にはアリエル・ピンクの音楽が少なくともある種の症状を緩和してくれるもののひとつだった。もちろん全ての薬には副作用がある。僕はずっとその副作用に苦しみ続けているのかもしれない。夢みがちで、皮肉屋で、独りよがりで、支配的で、脆く、見栄っ張りで、強情で、気難しく、不穏で、愚鈍で、何に対しても常に不満なのだ。
前回のコラム
執筆者:Naoya Takakuwa / ナオヤ・タカクワ
1992年生まれ、石川県出身。東京を拠点に活動するミュージシャン、作曲家。前身バンド、 Batman Winksとしての活動を経て、2017年、 ソロ名義での活動を開始。2018年にアルバムLP『Prologue』をde.ta.ri.o.ra.tionより発表。現在は即興演奏を中心に活動中。2019年には葛飾北斎からインスパイアされた即興ジャズ7曲入りCDーR『印象 / Impression』付きの書籍『バナナ・コーストで何が釣れるか』がDeterio Liberより刊行された。