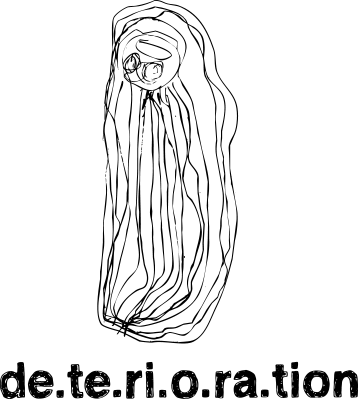MAGAZINE
ISSUE:03 Cairophenomenonsインタビュー「Single Seriesについて」前編

Cairophenomenonsは、音楽性も、世界観も、活動のペースさえも、すべてが独自だ。
他のバンドや音楽シーンの潮流に足を取られることなく、自分たちの呼吸と速度で進み続けてきた。
その特異な歩みは、メンバーそれぞれの強烈な個としての重力から生まれている。
結成から12年。バンドは、まるで異なる軌道を描く天体のように、何度もかたちを変えながらも崩れることなく、遠心と求心のバランスを保ちながら存在してきた。
彼らは、その絶妙な不安定さの中で、均衡とでも呼ぶべき何かを保ち、Cairophenomenonsという名の宇宙を構築してきたのかもしれない。
今回も前作『unfortunable believiewonder』に続いて、ナカムラ(gt / vo)を中心とした楽曲をリリースしている。
変化し続けるバンドに一貫して流れ続けてきたものとは何か。
その過程であらわになる「本質」とは何か──その輪郭を、今、掘り下げてみたい。
Interview Text by ムラカミカイ
──まずは、バンド全体の歩みについてうかがいたいと思います。ここ数年の大きな転機として、2021年に英詞から日本詞へと舵を切り、ドラマーの脱退、レーベルの移籍、さらには前作からナカムラさんが作詞やボーカルを担当したりと、Cairophenomenonsというバンドが大きく変わった印象があります。
ここ数年の、そうした変化は、意図的なものだったのでしょうか?あるいは、流れに委ねた結果だったのでしょうか?
ナカムラ (以下N):はい。2021年に、シングルで『MEKKI』って曲を出したんですけど、それがCairophenomenonsとして初めての日本詞の曲でした。それまでは全部英語でやっていて。でも、実はそのちょっと前くらいから、アラヤ(gt / vo)が英語で曲を書くのにちょっと行き詰まってて。「なんか、日本語でもやってみたいかもね」みたいな話は、ちょこちょこ出てたんです。まあ、僕も日本語やってみていいんじゃないかなって思ってたんですけど、なかなかバンドとしてそっちに舵を切れなかったんですよね。ライブはすでに決まってて、やる曲は英詞ばっかりだったから、そういう話も一旦止まってたというか。でも、ちょうどコロナ禍でめちゃくちゃ時間ができて。それで、アラヤの家に集まって、ちゃんとプリプロから日本詞で一曲作ってみよう、ってことになって。で、試しに『MEKKI』を作ったんですよ。そしたら曲自体もすごく良いものができたし、「じゃあこれ出してみようか」って。ちょうどそのタイミングでバンドからドラマーが抜けることになって、だから『MEKKI』のドラムは、当初、打ち込みで録る予定だったんです。でも、他のメンバーで上モノを録っていく中で、de.te.ri.o.ra.tionのタツキさんに音を聴いてもらったら「これすごく良いからドラムも生で録ろうよ」って言ってくれて。それで、ミツメの須田洋次郎さんにお願いして、叩いてもらうことになりました。
──2019年のAVYSS(アビス)によるインタビューでは、アラヤさん(gt/vo)が、「(人間のコミュニティの中で)どうも満たされないとか、欠落している何かがある部分を、(音楽によって)多分補おうとしているんだと思う」と語っていました。その流れの中で、「じゃあなぜ英詞で歌うのか?」という自身の問いに対して、「その方が気持ちいいから」とインタビュー中に自ら答えを導き出していたのがとても印象的でした。ナカムラさんも当時、「たしかに日本語だとどうしても違和感がある」と話されていましたが、あれから数年が経ち、今では日本語での表現を選ぶようになっています。言葉に対するスタンスや感覚に、何か変化があったのでしょうか?
N:バンドを始めた当初は、歌詞を響きというか、楽器みたいなものとして捉えてたところがあって。アラヤがその辺をどう思っていたのかは正直わかんないんですけど、まあ僕は、やっぱり歌詞も含めた良い音楽というか、歌詞の意味も含めた自分がいいと思う音楽を段々やりたくなっていったというか、個人的には、最初は響きを重視していたけど、バンドを続けているうちに、それだと音楽として弱いんじゃないかと思うようになって。やっぱり英語って、僕らにとって母語じゃないから、どうしても細かいニュアンスが伝わらなかったりするんですよ。そういう話は、たしかアラヤとも当時ちょっとしてた記憶がありますね。
──実際に、日本詞の曲をライブで演奏したり、音源をリリースしたことで、オーディエンスのリアクションはどうでしたか?
N:「日本語になっちゃったんだ……」みたいな意見は、SNSとかで見かけたりしましたね。やっぱり、聴いてる側にとってはけっこう大きな変化だったんだなって思いました。でも、やってるこっちとしては、そこまで大きな変化っていう意識は正直あんまりなくて。だから、ちょっと意外でしたね。
──個人的な意見ですが、聴いている側としては、日本詞になったことで、Cairophenomenonsが元々持っていた奇妙さとか歪さが、より剥き出しになったように感じました。
N:そうですね。それまでは、どこか綺麗にまとまってたところがあったと思うんですけど、日本語になったことで、もっとストレンジな感じが強く出てきたというか。もともと、パーソナルな部分では、メンバーそれぞれにそういう「歪さ」みたいなものはあって。英詞のときはある程度それが覆い隠されてた部分もあったけど、日本語で自由に書けるようになってからは、それがよりダイレクトに出てくるようになったのかもしれないですね。
──2019年のAVYSSによるインタビューでは、バンドを続けてきたことによる安心感や、音楽的な落ち着きについて語られる一方で、ナカムラさんとアラヤさんは、それぞれが「突き抜ける」「突き抜けたい」という言葉を何度も口にしていたのが印象的でした。
あの当時、お二人の中、あるいはバンド内で、その「安定」と「突破」の間で揺れていたような感覚があったのでしょうか?
N:ああ、その時から言ってたのか……(笑)
なんか、自分たちの中では、当時、バンドとしての個性がちょっと薄いなって思ってたのかもしれないです。少なくとも、僕はそう感じてたのかも。だから、わかりやすく言えば、「カイロといえばこのギターの音だよね」みたいな、そういうのが欲しかったんですよね。バンドとしての「らしさ」というか。そういうのを、もっとちゃんと出せるんじゃないかって思ってました。「これはカイロだ」って、聴いた瞬間にわかるようなものを、作り上げたかったんだと思います。
──それで日本詞になって、まさにMEKKIが剥がれ落ちたと……。
N:(笑)
 写真:ナカムラの制作机
写真:ナカムラの制作机
──ではここから、今回のシングル連続リリースについてうかがっていきたいと思います。今回も前作に続き、ナカムラさんを中心とした楽曲が並んでいますが、この一連の楽曲は、ひとつの大きな作品群として構想されているのでしょうか?それとも、一曲一曲がそれぞれ独立した作品として成り立っているのでしょうか?
N:一個一個はバラバラなんですけど、自分で作ってきた曲ばかりなので、なんだかんだまとまりはあると思うんですよね。というのも、影響を受けたルーツの音楽が一緒だから、その辺で自然と統一感は出てるのかなって感じはあります。ただ、意図的にこの5曲で何かまとまりを作ろう、っていうわけではなかったですね。それぞれを作曲した時期も違うので。たとえば『Neverhome』は、バンドが日本詞に切り替わったくらいのタイミングで、もうすでにやっていて。それがたぶん、2022年くらいですかね。ライブではその頃から演奏してた曲です。他の曲は、一昨年とか去年に作ったものが多くて、去年とか今年のはじめくらいからライブでやるようになった曲たちですね。
──今回の連続リリースには、前作『unfortunable believiewonder』とのつながりがあるのでしょうか?前作からの地続きとして捉えるべきなのか、それとも、どこかで断絶があり、新たなフェーズへと移行したものと考えるべきなのでしょうか?
N:うーん、そうですね。前作よりも、もっと洗練させたかったっていうのはありました。音像とかも、さらに作り込みたかったし、自分の中で好きな海外のインディの音っていうのを、自分なりに突き詰めて表現していきたいな、っていう気持ちは強くありましたね。音の質感という意味では、前作から地続きだと思ってます。ただ、今作のほうが、歌詞とか、日本語の曲としてのまとまりっていう部分では、よりしっかり形になったんじゃないかなって思ってます。
──それでは、連続リリースの第一弾『Neverhome』についてうかがっていきます。リリース時のプレス文では、レアード・ハントの小説『ネバーホーム』がインスパイアされた作品として挙げられていて、少し驚きました。文学が音楽に影響を与えること自体は決して珍しくはないですが、具体的な作品名が明示されていたのは、やはり印象的でした。あの小説は、どのようにして今回の楽曲と結びついていったのでしょうか?
N:たまたまなんですけど、『Neverhome』を作ってる時に、ちょうどあの小説を読んでたんですよね。で、読み進めながら曲も同時に作ってる、みたいな感じで。最初は歌詞よりも音の方が、その小説の雰囲気に引っ張られていった気がします。小説自体は南北戦争が舞台なんですけど、広大な土地とか、そのスケール感のイメージだったり、あとは、現実なのか夢なのかよくわからない、みたいな不確かな感覚。主人公が戦争に参加して、活躍はしていくんだけど、どんどん精神的に疲弊していっちゃって……みたいな話だから、その現実感の曖昧さというか。そういうのに、すごく影響を受けて作った曲で。まあ、作ってた当時は、そこまで意識してたわけじゃないんですけど、後から振り返ってみたら、「あのときちょうどこの本読んでたな」って思い出して。で、やっぱり歌詞が一番大変なんですよ。だからこそ、ちゃんと意識して、小説のイメージを取り込もうと思って、歌詞に落とし込んでいきました。なので、作曲中は、たまたま読んでた本にイメージを引っ張られてて、作詞の段階で「じゃあ、これをちゃんと題材にしよう」っていうふうに意識が切り替わった感じですね。で、最初の段階では、最後のパートはなかったんですけど、それも小説の世界観により近づけたくて、あとから作った部分です。
──小説『ネバーホーム』の翻訳で、翻訳家の柴田元幸氏はひらがなを多用し、重いテーマをあえてライトな文体で表現することで、独特の叙情性を生み出しています。
N:そうですね、僕は柴田元幸さんがすごく好きで。柴田さんが選んだ短編集とかも、よく読んでます。
──柴田氏は、アメリカのポストモダン文学を多く日本に紹介していますよね。
N:そうなんですよね。翻訳ものは、SF以外だとほとんど柴田元幸さんが訳したものばかり読んでます。たとえば、スチュアート・ダイベックの『シカゴ育ち』とか。あと柴田さんの訳じゃないけど、リチャード・ブローティガンも好きで、よく読みますね。
──ブローティガンについても、柴田氏はたびたび言及していますよね。
N:そうそう。なんか、物語があるようでない、みたいな、あの感じが好きなんですよね。ちょっとふわっとしてるけど、すごく印象に残るというか。

──このあと他の楽曲も順を追って詳しくうかがっていきたいと思いますが、今回のシングル連続リリースでは、他の楽曲にも本からの影響があるのでしょうか。また、これまでも文学作品が楽曲制作に影響を与えてきたことがあったのか、それとも今回は特別なケースなのか。そのあたりについても、お聞かせいただければと思います。
N:そうですね……。改めて考えると、自分で歌詞を書くようになってから、意識することが増えたのかも。これまでは、あんまりそこまで意識したことってなかったと思うんですよ。でも、自分で曲を書いて、詞までしっかり向き合うようになったことで、自然とそういうことを意識するようになったんじゃないかなって思います。
──音楽的には、この曲で意識した部分や、変化したところはありましたか?
N:基本的には、2010年前後のUSインディが未だに好きなので、そこから抜け出せないでいる感じありますね。ただ今回は、最後にシューゲっぽさも足して、インディだけじゃなく、もう少し包まれるような音像を目指しました。
──確かに、音の輪郭が柔らかくなった印象があります。包まれるような音像というのは?
N:たとえばリバーブの深さだったり、あと、今回、はじめて女性のバックボーカルを入れてみたんです。それもとてもおもしろかったというか。自分じゃ出せない声のニュアンスが加わって、音の重なり方が変わった気がします。

──続いて、6月にリリースされた第二弾『連敗』についてうかがっていきます。まず驚いたのは、Cairophenomenonsの楽曲としては初めて、タイトルに漢字が使われているという点でした。この言葉を選んだ背景には、どのような思いや意図があったのでしょうか?
N:これはもう、僕、野球がすごく好きなんですけど、去年、応援しているチームがシーズン前半すごく調子よくて。でも、途中からどんどん負けはじめて、連敗が続いてしまって(笑)その時期にこの曲を作ってたので、もうそのまま『連敗』というタイトルにしました。
──なるほど(笑)私的な感情の揺れをそのままタイトルに落とし込んだ、という感じなんですね。
N:そうですね。まあ「連敗」って、スポーツだけじゃなくて、日常でもいくらでもあるじゃないですか。曲自体はチームのことを歌っているんですけど、歌っているうちに、「別に自分も勝ち続けてるわけじゃないな……」みたいなことを思い始めて、自分と重なる部分が出てきた感じもありますね。
──サウンド面では、今回どんな工夫や挑戦がありましたか?
N:アコースティックギターは使ってないんですけど、フォークソングのイメージで作ってます。たとえば最後の部分なんかは、Whitney(米シカゴのインディー・フォーク/ロックデュオ)みたいな感じを意識しましたね。
──Cairophenomenonsとして、日本語のタイトルを出すことに抵抗などはありませんでしたか?
N:最初は、スタジオとかライブのリハで曲順をホワイトボードに書くとき、ちょっと恥ずかしかったですね。しかも、これからライブをするのに、ちょっと良くない言葉みたいな感じもあって(笑)
 写真:応援しているチームのユニフォーム
写真:応援しているチームのユニフォーム
──次に7月リリースの第三弾『Morning Haze』についてうかがいます。勢いのある曲調でありながら、どこか物哀しさも漂う、不思議な余韻のある楽曲だと感じました。歌の輪郭もはっきりとしていて、ファズサウンドとともに、言葉が強く響いてきます。この曲にも、制作の背景に影響を与えた本や作品など、リファレンスとなるものはあったのでしょうか?
N:これは、Real Estate(米ニュージャージーのインディー・ロックバンド)みたいな感じを意識して作ったところがありますね。特に最後の方は歪ませて、勢いのある感じにしました。『連敗』に続き、『Morning Haze』でも、Cairophenomenonsのライブサポートメンバーとしてお馴染みのクボくん(Jan flu、Puff、Machine Safari)がギターで参加してくれています。実は今回のレコーディングで、バンド以外の人がギターを弾いたのは初めてで、彼から色々アイデアももらって録音しました。だからこの曲は、オケのギターが何重にも重なっていて、ちょっとサイケっぽさもあって、良いインディ感が出せたかなと思っています。歌詞の最後に「意気地がないわ」というフレーズを繰り返しているんですけど、あれは当時読んでいた九鬼周造の『「いき」の構造』に「意気地」という言葉が出てきて、言葉の響きがいいな、あっているなと思って歌詞に取り入れましたね。
──『「いき」の構造』の第二章「いき」の内包的構造では、「いき」を構成する要素として、「媚態」「意気」「諦め」の三つが挙げられています。その中に出てくる「意気」、すなわち「意気地」という言葉ですね。
N:はい。歌詞を書いてるときに、ちょっと男女の物語っぽくなってきてて。駆け落ちしようとしてるんだけど、結局できない、みたいな雰囲気というか。やっぱ、そんなことできないよな、みたいなイメージがあって。で、なんか最後にハマる言葉ないかなぁって探してたときに、ちょうど読んでた『「いき」の構造』の中に出てきた「意気地」って言葉を取り入れた感じですね。まあ、別にこの本の哲学的な内容から強く影響を受けたってわけじゃないんですけど。昔の昭和の映画とか観てると、女性が「意気地なし!」って言ったりしてて、それもなんか良いなあって思っていて。なんだろう、根っこのところにあるのは、情けなさ、みたいな感じかもしれないですね。それは今回の連続リリースの全部の曲に、うっすら共通して漂ってる気がします。
 写真:ナカムラのギター
写真:ナカムラのギター
──Cairophenomenonsの楽曲では、これまでもファズサウンドが効果的に使われてきましたが、この曲ほど、言葉にアンダーラインを引くようなかたちで響くのは初めてのように感じました。ナカムラさんにとって、ファズというのは、どんな意味や役割を持つサウンドなのでしょうか?
N:「飛ばす」みたいなイメージですね。
──飛ばす……?
N:はい。昔、uri gagarnのライブを観に行った時があって。その時やってた曲で……
──『Mutant Case』でしょ!あの時、僕も会場にいて、ショウちゃん(ナカムラ)が「やべぇ、なんだあのファズ……」って何度もつぶやいてたの、今でも覚えてるよ!(笑)
N:そう、それそれ!(笑)あの曲でファズ踏んだ瞬間に、普通だったらもっとこう、音の芯がグッと前に出てくる感じを想像してたんですけど、あの時はなんかもう、「バーーーン!」って、爆散したみたいな音で。
──うん、あれは衝撃だった。
N:ね。ファズってこんな使い方があるんだ、ってほんと衝撃的だった。あの時からですね、ファズって、空間を変える、そこまでいたところから別の場所へ「飛ばす」みたいな。今いる場所から一気に別の次元に「飛ばす」みたいな。そういうイメージで使いたいなって思うようになったんです。2019年にリリースした『Prochet』という曲、あの曲も「飛ばす」イメージでファズを踏んでますね。
後編へ
Cairophenomenons(カイロフェノメノンズ)
ナカムラ(gt/vo)、マエノ(ba)、アラヤ(gt/vo)による3人組バンド。
Real EstateやDeerhunterを想起させるリバーブの効いたドリーミーでサイケデリックなUSインディーサウンドと、昭和歌謡のような朴訥なメロディラインが合わさった作品をコンスタントに発表しており、2024年7月にはEP『unfortunable believiewonder』をリリース。
2025年5月からシングル5ヶ月連続リリースを発表している。
Instagram
X
ムラカミカイ
I Saw You Yesterday、エイプリルブルーでギターを担当。
Instagram
X