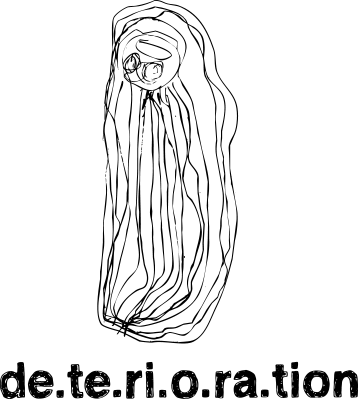MAGAZINE
ISSUE:03 Cairophenomenonsインタビュー「Single Seriesについて」後編

Interview Text by ムラカミカイ
前編からの続き
──8月リリースの第四弾『孤独の中』についてうかがっていきます。この楽曲も、第二弾『連敗』と同様に、日本語のタイトルがつけられています。また、楽曲全体からは、昭和歌謡やグループサウンズといった要素も感じられ、どこか懐かしさと新しさが同居しているような印象を受けました。この『孤独の中』というタイトルには、どのような思いが込められているのでしょうか。また、その言葉にたどり着くまでには、どのような経緯があったのでしょうか?
ナカムラ (以下N):これはもう明確に、USのサウンドとGS(グループサウンズ)を混ぜたいっていう試みがあって。歌詞も、七三分けの男の人がマイク片手に歌ってるようなイメージで書いて、そこからタイトルを考えた感じです。クボくんが「かなしい歌ですね」って言ってて(笑)。
──(笑)。グループサウンズは、どんなバンドを聴いてました?
N:僕は、めっちゃザ・スパイダースが好きです。あとはザ・タイガースも。その2バンドとザ・テンプターズのメンバーが集まって結成されたスーパーバンド、PYG(ピッグ)も大好きですね。沢田研二とショーケン(萩原健一)がボーカルの。
──USインディーもずっと好きで聴いてこられたと思うのですが、一方で、グループサウンズや昭和歌謡に惹かれるようになったのは、何かきっかけがあったんでしょうか?また、それらを今回、自分たちの音楽に取り入れてみようと思った理由や背景についても教えてもらえますか。
N:もともと、PYGは僕が高校生の頃に親戚の年上のお兄さんから教えてもらったんです。その人が音楽好きで、僕が「ナンバガを聴き始めた」って言ったら、『SCHOOL GIRL BYE BYE』を貸してくれたり、色んな音楽を紹介してくれるようなお兄さんで。その時「このPYGってバンドもかっこいいから聴いてみなよ」って言われて貸してくれたんですけど、当時は全然わからなかったんですよ。高校生の僕は、「暗いし、なんだこれ……」って(笑)。でも、段々ともっと音楽を知っていって、サイケとかを聴き始めたときに「GSもサイケとして聴ける」みたいな話をどこかで見て。それで掘り始めていったら、自然とPYGにも繋がったんですよね。PYGってGSのオールスター軍団みたいなバンドだから当然出てくるし、改めて聴いたらめちゃくちゃハマって。最初は、ザ・タイガースの岸部一徳(サリー/当時は岸部修三)のベースがすごく好きで、かっこいいなと思ってたんです。そこからどんどん掘っていって……でも、楽曲的に一番かっこいいなと思ったのはザ・スパイダースですね。曲がほんとに好きで。
──なるほど。今のお話をうかがっていて個人的に興味深いと思ったのは、先ほど(インタビュー前編を参照)の翻訳の話にも通じる点です。GSという音楽は、もともとビートルズやローリング・ストーンズ、ベンチャーズといったバンドの、日本版といいますか、日本的な解釈として流行したわけですよね。そう考えると、そこにもどこか繋がりを感じますね。
N:そうですね。日本人がそのまんま海外の真似をした曲って、実はあんまり売れてないんですよ。でも、歌謡曲と混ざったものが代表曲になってる。初期はローリング・ストーンズをそのままやったりしてるんだけど、それでもどこか味があるというか。結局、真似しても違うものになっちゃう。そこがおもしろいし、それが個性なのかな、って思いますね。この曲は、個人的にはモロにDeerhunterなんですよ。ドラムの感じとか、コードの使い方とか、リードもそうだし、Deerhunterをしたくて作った曲なんです。でも、そういう意味でも、僕らがUSインディをやったところで、同じにはならない。そこで自然と個性が出るというか。そういう部分に、GSへのシンパシーを感じるのもしれないですね。
──この曲のもうひとつの大きな特徴として、アウトロが約1分50秒と非常に長く取られている点が挙げられます。全体の尺が3分40秒ほどであることを考えると、その比重の置き方は異例とも言えるかと思います。あの長いアウトロには、どのような意図や感覚があったのでしょうか?
N:これはもう、長くしたくてめっちゃ頑張りました(笑)。2011年のPitchfork Music FestivalでのDeerhunterの『Nothing Ever Happened』の演奏があって。元は5分ちょっとの曲なんですけど、そのライブでは12分くらいやってて、ずっとアウトロを伸ばしてるんですよ。それがやりたかったんです。で、そこにクラウトロック的なイメージもあって。
──この曲にも、制作の背景に影響を与えた本や作品など、リファレンスとなるものはあったのでしょうか。
N:ちょうどこの曲を作っている頃に、たまたまポール・オースターの『ガラスの街』(柴田元幸訳)を読んでたんですよ。で、Deerhunterのボーカル、ブラッドフォード・コックスが、自分の中でその登場人物と重なっちゃって。『ガラスの街』に、めっちゃ話す人いるじゃないですか。何ページにも渡ってずっと喋り続ける人。あの人とブラッドフォード・コックスがリンクしちゃって、「この役やったらめっちゃハマるな」って勝手に思っちゃったんです。なんか、そういうふうに自分の中で繋がってましたね。
──このアウトロの長さにも通じていますね(笑)。(『ガラスの街』で登場するピーター・スティルマンの独白は15ページに及ぶ)

──9月リリースの第五弾『Days』についてうかがっていきます。この楽曲は、今回の連続リリースを締めくくる一曲となりますが、他の4曲と比べても壮大な印象を受けました。その位置づけや、作品群の中で果たす役割について、お聞かせいただければと思います。
N:これはライブでもやったことないし、練習すらしたことなくて、このリリースのためだけに作った曲なんですよ。で、この曲が一番、音色とか音像とかボーカルとか、かつてのCairophenomenonsっぽさがあるなって思ってます。リバーブが深くて、どろっとしてる感じ。僕はリバーブが深いことを「どろっとしてる」って表現するんですけど、そうやって全部が一緒くたになるのを目指しました。だからミックスも他の楽曲とは変えて、より大げさに、っていうか、そういう方向でやった感じです。イメージとしては、Deerhunterのギタリスト、Lockett Pundtのソロで、全編リバーブみたいなアルバムがあるんですけど、ああいう感じにしたいなっていうのがあったり。あとは『PERFECT DAYS』ですね。あの映画自体がすごく良かったって話じゃなくて、映画をきっかけにSNSで意見がめっちゃ割れてるのを見て、なんか嫌だなって思ったんですよ(笑)。気持ち悪いというか。なんだろうな、「あの生活がいいよね」っていう意見に対して、自分の中に違和感があったというか……。SNSで他人の生活ぶりを見て落ち込んじゃうことって自分にもあるんですけど、丁寧な暮らしを売りにしてる感じにどうも落ち着かないというか。
──なるほど。
N:金持ちの暮らしぶりだけじゃなくて、ああいう丁寧な暮らしみたいなのに、自分が押しつぶされそうになるのが、なんか嫌だなって(笑)。映画そのものが嫌いなんじゃなくて、あの映画に対する世の中の反応を見て出てきた感情が、この曲の歌詞に反映されてるのかもしれないですね。「完璧な日々が囲む私のすべて」っていう歌詞があるんですけど、その「完璧な日々」って、SNSや写真の中だけに存在するもので、実際はどうかわからない。でも、そういうのを見てると、勝手に自分が否定されてるような気分になっちゃう。そういうのが、嫌だなぁ……みたいな。
──映画『PERFECT DAYS』は、これもまた一つの「翻訳」、あるいは「変換」のように感じられました。海外の文学や音楽の翻訳とは逆に、日本という風景や暮らし、価値観が、ドイツ人監督ヴィム・ヴェンダースの視線を通して解釈・再構築されている。いわば「日本の翻訳」とでも言えるアプローチというか。その視線には日本人の忘れかけた情緒や美意識を丁寧にすくい上げる繊細さがある一方で、外から見た日本だからこそのズレや居心地の悪さも感じられますね。
N:うん、そうなのかもしれない。
──この『Days』を連続リリースの締めくくりに置いたことに関して、なにか意図があったのでしょうか。順番に込めた意味や、流れとして意識されたことがあれば、ぜひうかがいたいです。
N:『Days』は、いわばボーナストラック的な位置付けですね。バンドでもまだ合わせてないし、今回はミックスも全部自分でやったので。で、こういう大げさな曲が最後にあってもいいかな、まとまるかな、っていう気持ちがあったんです。

──最後に、今後のCairophenomenonsについてうかがいたいと思います。10年以上にわたって活動を続けてこられたCairophenomenonsですが、その中で世界や時代、バンド自体の表現の形は移り変わってきた一方で、ずっと変わらない部分や意識的に守ってきたことがあれば、ぜひ教えていただけますか。音楽的なことでも、バンドとしての姿勢や考え方でも構いません。
N:なんだろう……わからないな……。
──では、ナカムラさんが曲を作っていて、「これはCairophenomenonsっぽくない」と感じて持っていかないことはありますか。
N:あります、あります。シンプルじゃない、複雑すぎることをしてたら、カイロっぽくないかなって思います。なんだろう……。余白があるもの、かな。それと、Cairophenomenonsの楽曲は、やるせなさ。あまり正の感情じゃないかも。負の感情まではいかないけど。歌詞にしろ曲にしろ、なんかずーっとちょっと調子悪いみたいな曲、みたいな(笑)。
──ちなみに、アラヤさんは2019年のインタビューで「不満」と答えていました。
N:僕の曲は、不満までいかないかなぁ……。どうしようもないなぁ、みたいな。無力感。不可抗力。自分ではどうにもできないものに直面して、ただ立ちすくんでいる感じ。それに抗おうとか、そういうこともなく。でも別に受け入れてるわけでもない。そういうのが、僕にとってのカイロかな。それがカイロらしさかな。
──今回の連続リリースを通して、Cairophenomenonsとしての現在地がより明確になったようにも感じました。そのうえで、今のこのモードをもうしばらく続けたいのか、あるいはすでに次に試してみたい表現や方向性が構想としてあったりするのでしょうか?
N:新しいことに行こうとしてます。アラヤが戻ってきて、「ダブがしたい」って言い出して(笑)。
──ええ!ダブですか?
N:今そのセットを組んでやってて。卓にボーカルとドラムを繋いで、アラヤがイジる感じですね。めっちゃレゲエってわけじゃないけど(笑)。ちゃんとインディなんだけど、音像としてのダブ。まあしばらくはリリースした曲をライブでやりつつ、もし次回バンドで何か出すことになったら、また今までとは違う雰囲気になるかもしれないですね。
──ダブは意外でした(笑)。今後も、カイロの音楽がどう展開していくのか、とても楽しみです。
N:はい、楽しみにしていてください。

今回、ナカムラ氏に連続リリースについてインタビューを行い、強く印象に残ったのは、彼が複雑で奇妙な音楽を生み出しながらも、どこかギター少年のように純粋に音楽を作り続けている姿だった。
さらに興味深かったのは、自分たちの歪さがどこで生まれ、どこに本質や個性、面白さが潜んでいるのかを、ほとんど無意識のうちに理解し、その感覚を絶えずインプットしながら、自然にアウトプットへと繋げている点である。
連続リリース第一弾『Neverhome』は小説『ネバーホーム』(柴田元幸訳)を題材とし、そして第四弾『孤独の中』について、ナカムラ氏はポール・オースター『ガラスの街』をイメージのひとつとして挙げた。オースターの文体には英語にしか響かない乾いたリズムがあり、ニューヨークという都市の孤独をまるで音楽のように描き出している。その空気感や間合いは、直訳すればたちまち壊れてしまう。だが柴田元幸は独自の感性によって、それを巧みに日本語へと移し替えている。それは『ネバーホーム』の翻訳でも鮮やかに示されている。
“翻訳”とは、単なる置換、変換ではない。意味だけでなく、その言葉がまとう空気までも引き受け、価値観の層を掘り起こしながら、一つの植物を別の鉢に植え替えるように行われる繊細で大胆な試みである。そして時に、それは第三弾リリース『Morning Haze』がリファレンスとした九鬼周造『「いき」の構造』における「いき」のように、本来なら翻訳不可能なものへと触れようとする挑戦でもある。
訳すたびに概念は少しかたちを変え、揺らぎを帯びる。しかし、その揺らぎの中にこそ、本質や個性が浮かび上がるのではないだろうか。
これは、かつてグループサウンズが行った音楽的な翻訳とも通じる。
そして、Cairophenomenonsが英語詞から日本語詞へと移行し、USインディから強く影響を受けながらも日本語で歌うようになったことは、まさに彼らという歪な植物を、かつての鉢からより大きな鉢へと植え替える行為だったのではないだろうか。そして、ダブに手を伸ばすことも──。
彼らは、その”翻訳”における揺らぎの中に、自らの本質や個性、面白さを見出しているのではないかと感じた。
Cairophenomenonsという万華鏡の中で、彼らは自由に動き、偶然であり必然の美を放ち続ける。
その表現は、決して一つのかたちに収まることなく、光の加減や視点によって、つねに異なる像を結ぶ。
我々はその覗き穴を通して、彼らの表現だけでなく、世界の断片や、自分自身の感情の反射まで見ることとなる。
音がこだまする先に、なにが見えるか──それは聴き手ごとに異なるだろう。
だが確かなのは、Cairophenomenonsという名の宇宙が、いまもどこかへ向かって静かに膨張を続けているということだ。
今回の作品群が映し出した多面体の像の、その先に何が待っているのか。
我々はその続きを、きっとまた別の光でのぞくことになるだろう。
Cairophenomenons(カイロフェノメノンズ)
ナカムラ(gt/vo)、マエノ(ba)、アラヤ(gt/vo)による3人組バンド。
Real EstateやDeerhunterを想起させるリバーブの効いたドリーミーでサイケデリックなUSインディーサウンドと、昭和歌謡のような朴訥なメロディラインが合わさった作品をコンスタントに発表しており、2024年7月にはEP『unfortunable believiewonder』をリリース。
2025年5月からシングル5ヶ月連続リリースを発表している。
Instagram
X