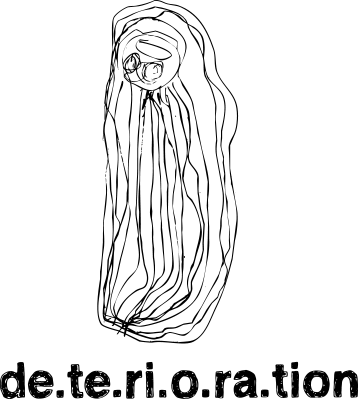MAGAZINE
ナオヤ・タカクワの日記〜2020.07.24-07.30
7月24日(金)
今朝トイレに入っていた時のことだ。用を済ませて立ち上がると、ズボンのポケットに入っていた携帯電話が小さな放物線を描いて、便器の中に着地した。用を足しながら画面を触っていて、立ち上がる際に下ろしたズボンのポケットに入れたのだが、それはうまく奥の方まで入っていなかったのだろう。ズボンを上げた瞬間すっぽりとポケットの中を抜け出して行ってしまった。
少しの間、僕は便器に横たわったそれを眺めていた。画面には現在の時刻が表示されていた。見たところ何の問題もなさそうに見えた。それでも、僕の携帯電話には防水機能だとかそういったものは付いていなかった。体の限界を迎えて、熱中症と火傷を併発しながらも、平気な顔でサウナの中に居座る男のようなものだったのだろう。もしくは、やがて飢餓により死ぬまで座禅を組み続けた達磨大師のようなものだったのかもしれない。この二つの比喩は全く同じようなものだと人は言うだろう。そしてこの二つを並べることは失敗だったと人は言うだろう。それでも僕はやはりこの二つの陳腐な比喩を並べざるを得ない。それは密かな心的動揺によってもたらされたのかもしれない。
自分の心的動揺について考察している内に、携帯電話はさらに奥深くへと沈み込んでいった。哀れな携帯電話。しかし一番哀れなのは携帯電話ではなく、僕かもしれない。そもそも、携帯電話は痛みや感情を一切持ち合わせていない。それに対して、僕は生物としては高度な感情を持っているホモ・サピエンスである。その、ホモ・サピエンスである僕が、主要な世間との連絡手段を失ったという点については憐れむべきことだと言える。問題なのは、僕を憐れむ存在がいないことだった。僕は携帯電話を憐れむが、僕のことは誰が憐めばいいのだ?
携帯電話を壊すことは、僕の人生の重要な位置を占めていると思う。いつだってそれが転換期だった。連絡手段を失うことは世間からの逸脱を意味する。それはある種の孤独を呼ぶが、ある種の平穏をもたらすものでもある。僕はそんな無音の世界でじっくり耳をすませる機会を、携帯電話の破壊により享受することができるのだ。
7月25日(土)
携帯電話を注文して、明日届くように手配した。
昼飯を食べに定食屋に行くと、二人の老人が江戸っ子なまりで喋っていて居心地が良かった。しかし彼らの口角から飛ぶ唾液の飛沫のことを思うと、気が気ではなかった。
彼らは普段の夕食メニューについて議論していた。コンビニの弁当に飽きたため、オリジン弁当を買っていると一人の老人が言っていた。僕はここだけの話、オリジン弁当で働いていたことがある。オリジン弁当の揚げ物はなかなかのクオリティだ。もう一人の老人が「餃子の王将」はどうだと言った。「王将はまずい」ともう一人の老人が言った。
僕は王将はそこそこ美味いと思う。
7月26日(日)
注文していた携帯電話が届いた。宅配員は少し申し訳なさそうに伝票を出してきて、僕はそれにサインをした。ひどく強い雨が降っていた。雨は一粒一粒がハマグリほどの大きさをしていた。それにその一粒一粒に奇妙な薄ら笑いの表情さえ見て取れた。何かとてつもなく悪いことが起こるような予感がした。彼は濡れた帽子に手をかけて一礼すると雨の中に戻っていった。雨。とても長く続く雨だ。今日も明日も明後日も雨だ。それらの雨をくぐり抜けて、晴れ間がのぞくと僕たちは少しすっきりした気分にもなるし、あまりの暑さにうなだれたりもする。それらは気温と湿度の相関関係により引き起こされる感情的起伏であり、「不快指数」と呼ばれる計算方式が夏の暑さを不快と感じるおおよその目安として機能している。
我々はこの不快指数を人工的に減らすために様々な製品を開発してきた。手乗り扇風機、ユニクロが開発した合成繊維である「エアリズム」のシャツ、ポリエステルの短パン、長時間歩いても疲れないサンダル、首元を冷やす冷感タオル。多くの人々は休日に街に出るのに、それらの製品を身にまとっている。我々は科学と工業の力により夏の蒸し暑ささえ克服できるのだ。太陽はとてつもなく巨大だが、それがもたらす忌まわしき効果を最小限に止めることは、我々にとっていとも簡単である。
僕は少なくとも、エアリズムのシャツや短パンや冷やしたタオルやサンダルを使わない主義であり、夏は汗で濡れて肌に張り付いてしまったシャツや、特にお尻の部分が汗染みで暗い色になったスラックスを履いて出かける。夏の不快感を享受し、不快である快楽を享受する。不快であることが快感であるというのは、この世界を構築する全ての現象の心理ではないか。例えば……いろんなことを思い出してみてほしい。空腹が限界に達したとき。それとは逆に食べ過ぎた時の胃の不快感。眠気に耐え、夜が明けた次の日。ホラー映画を観ること。携帯電話を持たないこと。全ての快感はマゾヒズムに起因しているのだ。
「ちょっと待てよ。携帯電話を持たないことを不快だと感じ始めたのはいつ頃だったっけ?」
僕はすでに携帯電話を持たないことに快楽を感じ始めていたし、その欲動を止めることはもはやできなかった。雨の中の宅配員から携帯電話を受け取った瞬間に、僕はその快楽を享受する行為が、あえなく無効化されてしまったのだ。それはあくまで、手元に携帯電話がないために、享受できる種類の快楽だった。それは可能性に関係したことであり、手元に可能性が戻ってきた限り同じ快楽は復元不可能となった。
しかしながら、僕は先ほど述べた種類の快楽を享受できないことに起因する不快感、それを感じ続けることでまた新たなマゾヒスティックな歓びを見つけるだろう。不快と快楽は隣合わせでお互いに背中を向いて立っていながら、視線を送り合い口元に笑みを浮かべている。そう、彼らはいつだって二人で一つなのだ。
何かを不快に感じたときには、その光景を思い浮かべてみてほしい。きっとあなたのマゾヒズム的精神構造が、重い腰を持ち上げて大きなねじを回しだす。それからあなたは、笑い出したいような気持ちになり、永久に続くかのような快楽に身を埋めていくかもしれない。
7月27日(月)
帰ったらいつものヤモリが壁に張り付いていたので「やあ、こんばんは」と声をかけてみた。ヤモリは「ヤア、コンバワ」と言った。あまり彼は日本語を喋るのが得意ではないのだ。僕らはそのあと少し気まずい沈黙の時間を過ごした。気まずい沈黙も、必要とされることはあるのだ。例えば、そう、二人のお互いに気がある人間が同じ部屋にいて、気まずい沈黙を過ごすというのはいいものだ。沈黙の中で、熟成されていくものが確実にある。そうした場合、何もしないことが何より重要なのだ。例えばヤモリに向かって不用意に手を差し出せばヤモリは逃げ去ってしまうだろう。そのあと僕は、なんとも言えない孤独に似た何かに身体中を支配される。ふとそこにあった何かが消え去ってしまうときの感覚だ。
それは映画のエンドロールが始まったときの感覚に似ている。それは本を読み終えてしまったあとの感覚にも似ている。そして、ガラスのコップを割ってしまった時にも少し似ている。それらは似ているが少しずつ違う喪失だ。そしてそれは祖父を失ったときの喪失感とは全然違うものだ。
しかしやはりこの喪失感を言い得て妙だと思えるのは、さっきまでお腹を向けて僕の前に転がっていた猫がふとした瞬間に立ち上がりどこかに行ってしまって、そのあとこっちを振り向きもしないことだ。それは女の子にフラれた喪失感よりも、もっと大きい。それは彼らの存在が、理性と理性ではない部分の混ざり具合がちょうどいい具合になっているからかもしれない。そこにはスイッチのようなものがあって、脳の回路が切り替わる瞬間がある。
その猫の行動を見ていると、あたかも自分の住んでいる世界が、実在しないものであるような錯覚に襲われるのだ。偽の満足感。偽の快感。偽の友情。そして、僕の思考も感情も身体も全て偽物で、猫が行ってしまった「あちら側の世界」が本物なのだと、そう信じざるを得ない。
7月28日(火)
何をしたか忘れてしまった。本を買いに行った気がするが、本を買いに行ったのは明日だった(そう、僕は未来からこの日記を書いている)もちろん、行きつけのブックオフへ行ってきたのだ。今回はその買い物内容を紹介しようと思う。
『オラクル・ナイト』
ポール・オースターの本。オースターの本にしては安く売っていたので買っておいた。確か260円ぐらい。まだ彼の他の作品を途中まで読んで投げ出したのが本棚の隅っこにあるのだが。仕方ない。出会いは出会いであるからだ。ブックオフでは本と出会ってしまったら買わなくてはならない。
『ウディ・アレンの時代』
1987年に発刊された本だ。やはり多少カビ臭い。それでも多数のカラー写真やモノクロ写真も付いているし、380円ぐらいだった。
『バスキア ザ・ノートブックス』
昨年開催されたバスキア展で展示されていた、ノートブックの落書きがとてもよかったので購入した。これは、対訳も付いている。バスキアの書く詩(のような何か)に対訳が必要なのかどうかはわからない。それでも少なくとも参考程度にはなるはずだ。馬鹿みたいだが、2500円ほどした。本当は、馬鹿みたいではない。煙草を5箱並べた横にバスキアを置いてどちらをとるかという問題なのだ(少なくとも僕のような生活が逼迫している人間にとっては)または、やよい軒の定食を3食分並べた隣にバスキアを置いて、どちらをとるかという問題なのだ(僕はこの場合もしかしたら定食を食べてしまうかもしれないな、と少し思った)
7月29日(水)
とんでもない量のアルコールを摂取した。それにより、僕の自我はほぼ消滅し、故にこの世界も本来あるべき姿を失っていた。暗い闇の底から明かりを灯すバーに入った。僕はもはやすでに意識というものを持っていなかった。
もつれる足を引きづりながら、中に入るとどでかい椅子に座らされた。まるで牛の上に座っているような気分だと僕は思った。バーテンの声は限りなく小さく、店内で流れるクール・ジャズ・スタイルの音楽にかき消されてしまいそうだった。その声は、暴風の中に立っている一本のロウソクの火のように消えかかっていた。それでも完全に消えてしまうことは永遠になかった。
なんとか彼とコミュニケーションをとり一杯の酒を注文した。椅子の中でもぞもぞしているとほとんど半自動的に酒が出てきた。バーテンは「よく冷たいと言われるんですよ」と話していた。彼の人格についての話だったが、用意されたドライマティーニも氷のように冷たかった。
冷たい酒も、ゆっくり飲んでいるとぬるくなってきた。バーテンの冷たさも段々と穏やかなものに感じられてきた。我々は時間の経過により、人格すら変化していくことを目にする。僕らは電子レンジを持っていればそれを暖めてやることができるし、冷蔵庫を持っていればキリリと冷やしてやることすら可能だ。ウイルスに犯されることで、我々の抗体か何かが働き体温は上昇する。低血圧で冷えた体も、電子レンジで暖めたように沸騰してくる。その温度の上昇が、少しだけならばいいのだが。
7月30日(木)
二日酔いの体を背負って仕事に向かうのは決して気楽なことではない。僕はなんとか定時の電車に潜り込むことができたが、職場までかかる時間がいつもの何十倍かに感じた。カバンの中に入れてきた本だって読む気がしなかったし、騒音をシャットアウトするためのイヤフォンを耳につけることすら不可能だった。つまり、僕の右手はつり革に塞がれているし、左手はダランとして機能不全に陥っていた。立っていること自体が苦痛である。だけど僕はれっきとした一人の成人男性として、本来座るべきところ以外に座り込むことは断固拒否した。これはプライドの問題なのだ。人類はプライドのおかげで様々な精神的疾患を患い、物理的な殺し合いをする生き物なのだ。つまり、それは「勝ち負け」であり、比較から生まれるものは憎しみでしかないということだ。それを知っていながら僕がプライドを維持し続けようとしてしまうのは何故なのか、ということは様々な心理が科学的に解明された(いや、解明はされていないが多くの真っ当だと思われる仮説が沢山存在している)現代において大きな謎として、僕の精神の真ん中にどっかと生えている巨大な植物の幹の上にもたれかかっている。そしてもちろん僕は答えを得る。僕は比較対象としている仮想敵(のようなもの)は過去の僕自身である。それにしても本来「勝ち負け」など存在していないはずなのだが。
過去の自分のことを思い返すとき、その情けない情景を思い浮かべるとき、僕はクラクラとしてくる。それらは現在の自分の有様を否定し、陵辱し、侵食してくる。僕は過去の自分に箸で持ち上げられ、口内に運ばれた後ゆっくり咀嚼され、飲み込まれたあと胃で消化されてしまうのだ。そうならないための防衛策としてプライドや自分で決めた雨もあられもないルール、価値観を持って「勝ち負け」を決めるのだ。そして、過去の自分に自分の作ったルールの中で負けないように努力する。それがなんとか僕が今日も自我を保ち、平常心で生活するための唯一の方法なのだ。そんなものが必要なくなったらもっといいのだが。
続く
前回までの日記
執筆者:Naoya Takakuwa / ナオヤ・タカクワ
1992年生まれ、石川県出身。東京を拠点に活動するミュージシャン、作曲家。前身バンド、 Batman Winksとしての活動を経て、2017年、 ソロ名義での活動を開始。2018年にアルバムLP『Prologue』をde.ta.ri.o.ra.tionより発表。現在は即興演奏を中心に活動中。2019年には葛飾北斎からインスパイアされた即興ジャズ7曲入りCDーR『印象 / Impression』付きの書籍『バナナ・コーストで何が釣れるか』がDeterio Liberより刊行された。