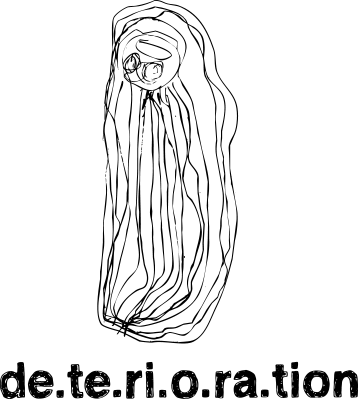MAGAZINE
ナオヤ・タカクワの日記〜2020.08.21-08.27
8月21日(金)
今日も暑さが肌を刺す。千本の針が上空から降りてくる。全て肌で受け止めてもまだ足りない。暑さは刺す場所を求めている。蚊と同じだが、音を立てない分いくらかましだとも言えるし、その逆だとも言える。日光はアパートメントの前に落ちていた鼠の死骸も消し去ってしまった。夜は全てを消してしまうし、それは朝になっても復活はしない。キリストが復活するのは聖書の中だけであって、スティーヴ・ジョブズもマイケル・ジャクソンも渡哲也も復活しない。他の多くの命と同じように、便器に落とした携帯電話も復活しなかった。携帯電話はスティーヴ・ジョブズよりは復活する可能性が高かったが、それでも無理だった。
作曲をしようとしてコンピュータの前にギターを持って座ってみるがメロディは浮かばない。何枚かの五線紙を白紙のままゴミ箱に入れた。丸めて、ゴミ箱に入れると、それは音楽のようだった。一枚目の五線紙はバッハのフーガみたいだったし、5枚目のそれはブーレーズみたいに見えた。音楽は聴く物ではなく、見る物なのかもしれなかった。それが一番の勘違いだったのだ。人類は音楽を耳で聴く物だと思っていた。コンサートに行っても、演奏を見る事はあっても、音楽自体を見ようとはしなかった。音楽は見る物だし、映画は食べる物だし、暑さは刺す物だし、絵画は嗅ぐ物だ。
カフェに行っていくらかの食べ物を嗅いで、ワインを触った。煙草を何本か打った。一本はホームランにしてやった。
8月22日(土)
ヨガをやって、白雪姫を観た。
小人たちはインディアンで白雪姫は入植者に見えた。
ディズニーランドは今、空いているだろうか?
夜に雨が降った。雷がたくさん鳴った。
そしたら眠くなってきた。
妻と一緒にベッドで白雪姫を観ていた。
途方もない一つなぎの時間が徐々に輪郭を失い、我々は眠りに入る。
8月23日(日)
午前5時に起きて、朝食の代わりにコーヒーを飲む。コーヒーを淹れるのはちょっとしたコツがいる。僕は旧式の電気式コーヒーメーカーの復刻版を使っている。僕のやることは、コーヒーメーカーに水を入れて、ドリッパーに紙フィルターを付けて、その中にコーヒー豆を入れる。あとはスイッチを押すだけだ。しかしコーヒー豆の分量を少しでも間違えてしまうと、とんでもなく不味いコーヒーが出来上がってしまう。豆と水の量の問題なのだ。僕はコーヒースプーンのすり切り一杯より小指の爪1個分多い分量をスプーンで慎重に測る。
その際に色々なものが邪魔してくる。暑さ、湿気、虫の羽ばたく音、今日の予定、明日の予定、それらの全てが脳内に侵食してくる、そして僕がコーヒー豆の入った缶にスプーンを差し込む行為を失敗させようとしてくるのだ。3回、缶にスプーンを突っ込むのに失敗した。これは命懸けの仕事である。ちょっとやそっとの神経では成し遂げられない偉大な仕事なのだ。汗が額に滲んでくる。肌をつたってまつげの上に水たまりを作る。午前5時に起きたばかりの脳内は正常とは言えない。少なく見積もっても異常である。言葉を選ばずに言うなら、死の一歩手前というような精神状態だ。そのような精神状態で、僕はヘア・バンドを頭につけ忘れてしまった。そのおかげで僕の目の中には大量の汗が入り込んできて洪水状態だ。
洪水が起きた時にはどうするか?もちろん、高台に逃げるのだ。僕は部屋の中で一番高い部分――キッチンのシンクの上に駆け上った。身体が流されてしまわないように。
なんとかそれに成功した。洪水は過ぎ去った。シンクの上には朝日が差し込んでいて、しっかりと僕の瞼を乾かしてくれた。自然のものを使うのが一番だ。僕はこういう時にヘア・ドライヤーを使って電気的な力で瞼を乾かすやり方は好きではない。電気のことはあまり信用していないからだ。いつ停電になるかわからないし、何に使ったのかまるで覚えていない高額の料金を毎月請求されるからだ。それに電気は目には見えない。僕は自分の目で見たもの以外は信じない主義なのだ。だから、U.F.O.も、幽霊も、死後の世界も、酸素や窒素の存在も信用していない。僕たち人間の身体は通常呼吸により酸素を取り込んで二酸化炭素を吐き出している、と言われている。だけど、その動きを目で見た者はいないし、僕は窒素を吸い込んでアンモニア水を吐き出しているのかもしれないのだ。その意味で、普通に呼吸するより、煙草を咥えている方が居心地がいい。居心地というのは地球の上で生きる気分のことだ。そして、煙草を咥えると、煙の影響で空気の流れを目で追うことができるようになるのだ。
シンクから降りたあと、なんとかコーヒーを作ることに成功した。今日はうまい配分で出来たはずだ。これ程苦労して仕上げた物が、大したことが無ければ報われない。これから生きていくこと自体が心配になってくる。努力は報われると教わって生きてきたからだ。努力がいかなる形でも報われない場所に僕は住むことができなかった。それは教育のせいだった。教育なんて受けなければ毎朝起きてすぐにトイレへ入ったり、「おはよう」と挨拶したり、一日に数十件くる携帯電話の無駄な通知に煩わされる必要はなかったのだ。
そんなに美味くないコーヒーが出来上がったのでもう一度寝た。眠りは裏切らない。眠ったあと起きると、毎回しっかり時間が経っているものだ。
8月24日(月)
1週間ほど、運動を辞めてみると調子がいい。運動をすることは必ずしも「健康的」とは言えないのではないかと僕は思う。世間は健康であるためには、運動が必要だという考えを押し付けがちだ。そもそも僕の身体が健康上問題がないことが、運動は不要だということを証明している。15歳になる1ヶ月前から18歳の半ばまで、ほとんど家から出ることなく、もちろん運動もしない生活を送ったが、少し背骨が曲がったとは言え、健康上なんの問題も持っていない。問題があるとすれば、右脇腹にある大きなほくろが時折痛むぐらいだ。
しかし、僕も自分の痩せて骨ばった身体を鏡で見ると、恥ずかしながら劣等感のような物を感じて(それが誰、もしくは何に対する劣等感なのかはわからない)運動を始めることにしたのだ。インターネットが完全な形で整備されている現代において、僕たちは様々な方法での運動の方法を知ることができる。特に、スマートフォンは偉大な携帯端末であり、いつどこにいる状態でも、様々なエクササイズ方法、増量法、ストレッチ方法、筋力を最大限増加させるためのトレーニング・スパンをそれぞれ調べることができる。ナイキの出したトレーニング・アプリを使って、1ヶ月のトレーニング・メニューを組んだ。と言っても、僕が直接組んだわけではなく、体重、身長、年齢、週に何度トレーニングをするか、1回につき何分間行うか、を入力していっただけだ。あとは、コンピュータが計算して、僕に合ったトレーニング・メニューを弾き出してくれる。
何週間かそのメニューに従ってトレーニングを続けたが、それにより僕は文化を摂取する時間や気力、体力を失ってしまった。本を読む時間、映画を観る時間、ギターを練習する時間、音楽を聴く時間、物を書く時間、座禅を組む時間、様々な時間が僕から失われていった。そして、気力、体力も。
トレーニングを辞めたことにより、今日の僕は頭の中がはっきりと冴え渡っている。見ての通り、キーボードを打つ手の動きからそれは見て取れるだろう。まるでへびが獲物を捕らえるときのような素早い動きが連続して続いていく。その連続性は、ある種の永久機関さえ思わせる。永遠に指の動きが止まらないのではないかと思えてくるのだ。しかしそれだっていずれは杞憂に終わることはわかっている。この数分後には手をキーボードから離して、コーヒーカップか小説本に手をかけていることだろう。そして驚くべきことに、ここまで書いて気づいたのだが、今日は何ひとつ面白いことを書いていないのだ!ギャグを言えないコメディアンに何の価値があるだろうか。僕はしっかりとした反省の気持ちを抱きながら、そろそろ今日の日記を終わらせることにする。書きたいことはたくさんあった。今日もいろんなことが起こったのだ。しかしそれを語るには、もう、書きすぎた。いずれ、それらのことを語ろうと思う。それまで読者諸君が待っていてくれたらいいのだが。もしくは待っていなくたって構わないかもしれない。どちらにしても同じようなことだ。
8月25日(火)
映画『白雪姫』について僕はいよいよ語ろうと思う。1937年の公開時にはセンセーションを巻き起こしたこの作品を僕が再度観ることになったのは、古典回帰的欲求の表れであると思う。古典回帰、しかもディズニーアニメーションであるということは、僕を就学前児童の思考状態まで退行させることである。子供のときは、大人になりたくなかった。大人になった今、子供には全然戻りたくない。結局、大人と子供のどっちが良かったのか。それは過去の自分自身を出来るだけ完全な形で呼び起こすことでしか達成しうることはない。
古典的名作である『白雪姫』はシンプルな構造を持つ作品であるがゆえに、幼少期にこの映画を見せられた我々は一種の麻痺状態に陥り、その本質を理解することはできなかった。20代も半ばを過ぎたいわゆるアラサー世代により、再鑑賞されたそれは著しく趣が異なってくると思われる。ディズニー映画に端を発するアニメーション群は子供たちに世話を焼かずに済ませられる格好の道具として親たちにもてはやされた。特に、僕が生まれた1992年にはすでに、家庭に据え置きのスクリーン、TVを利用したビデオ・システム、VHSがどこの家庭にもあるのが当たり前だった。我々は生まれて間もない頃から、現実と剥離したもう一つの世界、アニメーションの世界を同時に生きていく宿命を背負わされる。
アニメーション映画の特徴は、現実をモデルとした絵作りやストーリーを持ちながら、それはカメラのレンズを経由していないことだ。カメラを通した映像は幾分現実世界にフィルターがかけらえれているとはいえ、現実世界をそのままの形で写しとろうとした物だ。カメラを用いた映像は、いわば、現実の加工と言える技術である。それに対して、アニメーションはもう一つの現実を作りだす作業に等しい。いわば現実世界を人間の手でコピーし、創造しようとした世界だ。この世界では人間は本当の神である。
『白雪姫』の話に戻ろう。『白雪姫』はウォルト・ディズニーによる初めての長編アニメーション映画だ。特筆すべきは、ディズニー映画の中で初めて「人間」が描かれたということだろう。それ以前は人間以外の動物をモデルとしたキャラクターが走り回るのがアニメーションの通常だった。人間を描くことで、もう一つの現実世界を獲得しようとしたということは、今後のアニメーション界の規範となる。
幼少期の記憶にあった白雪姫像は、朧げなものだが、老婆に化ける魔女が悪で、主人公の白雪姫が善だという物だった(こうした二元論が果てしなく無意味であることに我々子供たちは気づくことができない)。そして動物たちは善だが、小人たちは善なのか悪なのか判断がつかなかった。僕らは白雪姫の生き方を手本にして生きていこうと誓うことになるだろう。なぜなら、彼女は動物からも小人たちからも愛されている(魔女は別としてだが、魔女はどちらにしたって悪として書かれているので好かれる必要はない)。我々はもちろん愛を求める自然的欲求を皆持っているし、愛を得るための方法として、白雪姫のようになろうと無意識に誓わされるのだ。
我々は『白雪姫』を鑑賞する前は小人たちだった。清潔さや紳士的な態度がなぜ必要なのかを知らなかった。しかし、鑑賞後にそれはわかる。つまり愛だということだ。そしてそれが大人になることだと、14歳の少女、白雪姫から学ぶ。14歳は立派な大人かもしれない。少なくとも、未就学児童にとっては。
しかし、歳を食ってから観る『白雪姫』からは全く幼少期とは異なる印象が浮かび上がってくる。まず、白雪姫は全く善ではないということだ。白雪姫がこの映画の中でやったことをおさらいしておこうと思う。そうすることはこの映画を体系立てて理解し、論理的結論を導きだす支えとなってくれることだろう。
白雪姫が義母により殺される寸前まで追い詰められるところから物語はスタートする。身の危険を案じた白雪姫は森に逃げ込む。ここで重要なのが、義母が白雪姫を殺そうとした理由である。義母は鏡に一番美しいのは誰かと尋ねる。鏡に尋ねているというのがポイントであり、これは自分の心理状態を映す鏡として機能している。そして、一番美しいのは白雪姫だと鏡は語る。いうまでもなく、美しさとは主観的なものではなく、誰が最も美しいかを決めることはできない。鏡がそう語るのは、義母が白雪姫を一番美しいと思っているということなのだ。白雪姫の美しさへ嫉妬した義母は自分がさらに美しくなろうと努力をする代わりに、白雪姫を排除し、自分が最も美しい者になろうとするのだ。それは本質的な美しさを手に入れることではない。美しさが主観上のものであるにせよ、自身の価値観においての美しさを手に入れようとするわけではなく、美しさそのものを排除しようとしているのだ。それは自分の美しさへの執着と、それに対する疲弊のため、理想からの逃避を試みようとしていると言い換えることができる。
理想からの逃避自体は悪い行いであるとは僕は思わない。それは一種の解決策である。特に思春期に、人は理想と現実の剥離に悩まされることになるが、解決策の一つが理想の排除である。理想を排除することで、ありのままの自分の姿が一番美しいと思える。そうした流れは非常に精神的成長を表す動きである。しかし、この映画においては、理想の排除が「死」と結び付けられることで、「理想の排除=悪」の図式を作り出しているのだ。ウォルト・ディズニーが、理想を永遠に追い求める人間であったことが、何らかの形で関与したことは間違いないだろう。
また、それはアニメーション映画自体を肯定する役割も担っている。一種の、アニメーション作者としての言い訳と言えるだろうか。つまり、アニメーション映画自体が、理想化された現実という側面を持っており、その理想化された現実の排除は悪であるという保身的結論を裏付けるためにも「理想の排除=悪」を物語の構造に適用しているのだ。
物語の流れに戻ろうと思う。
白雪姫は義母の殺意から逃れるため、森の中に逃げ込む。森の中で動物たちに囲まれて、彼女は「オタサーの姫」状態になる(「オタサーの姫」が白雪姫に由来しているのかもしれないが、そんなことはどうだっていい。何しろ、「オタサーの姫」という言葉があまりにもしっくりくるのだから)。動物たちが魅了されたのは、森の中には今まで存在し得なかった姫の美貌、そして美声である。ここで驚くのが、姫は、動物を助けたことによって動物に好かれる、というような善意の行動を全くとっていないことだ。ただ、彼女の美貌を持ってして野獣たちをてなづけたのだ。ルッキズムでしかない姫の描写は2020年代を生きる我々未来人の目にはあまりに無神経であるが、1930年代においてはその点が全くもって問題視されていなかったであろうことは想像に難くない(何しろこの映画の公開から既に83年の月日が流れているのだから。83年というと長寿の人間の寿命にぴったりである)。そして彼女はあろうことか、動物たちにこう語りかける。「私は貴方達のように、地面で寝ることはできないわ」そう、彼女の中の「姫」が頭をもたげる。あくまでも城に住む貴族であるという属性はどれだけ過酷な状況に置かれようと失われることはない。彼女は下々の者どもと枕を共にすることはできないのだ。しかもそれは彼女のプライドのためであるようには見えない。彼女の成長過程における豪華な生活環境への慣れが、外部の環境への適応を拒んでいる、それも自然に。一度、甘い汁を吸ってしまった者は元の生活には戻れないのだ。それでも、姫は権力を行使し、元の生活形式を取り戻そうとする。
さて、動物たちをしもべとした姫は彼らに連れられて、森の奥へ向かう。そこには小人達の住む小さな家があった。そして小人達は仕事中のため留守にしていた。姫はその他人の家に不法侵入を試みる。そして、勝手に部屋の中を掃除し始める。掃除が表すのは清潔さであり、フロイトが言っているように、人間の文化の形成、発達には清潔さが不可欠であるとされる。未開の地に文化を持ち込み侵略していく様は、インディアンの住むアメリカ大陸に乗り込んできたヨーロピアンを思わせる。そして、彼女は自分が箒を持ちはしたといえ、ほとんどの重労働――皿洗いや埃払いなどを動物たちにさせている。自分は楽をして(しかもこれは自分の寝床を快適な状態にするためなのだ)労働を強いる姿はまさに資本家そのものだ。しかも、それらへの報酬は全く支払われることはない(動物たちにとっての利益は何一つない)。まさに奴隷のような扱いで動物たちを働かせるのだ。しかもそれは権力や暴力ではなく、美貌を持ってなされるというファンタジー性は幻想的な絵作りも相まって、それが夢の中であるような、しかもとても楽しい夢であるような錯覚に視聴者を陥れるのである。この映画をみた子供たちはこの視聴覚の快楽により、パブロフの犬的原理によって清潔さそのものに対して快感を得るような感覚を培うことになるかもしれない。
そして、小人たちが帰ってくる。
彼らは自分たちの家に起きた異変に気づく。しかし白雪姫はもうベッドで寝てしまっている。小人たちを動物たちは怖がらせようとする。一足先に文化を手にした動物たちは妙な優越感に浸っているような表情で、様々なやり方で小人たちを恐怖へと導く。そう、すでに動物たちは白雪姫の支配下にあり、姫は自分が寝ていてすら、周囲に影響を及ぼしうる存在となっている。森というエコノミーを支配することで、自らは手を動かさなくても、利益を生み出すことができる怪物と化したのだ。これはウォルト・ディズニー氏の当時の状況を反映していると考えられる。ミッキーマウス等の短編作品で手にした利益で、アニメーターを大量に雇い、自らは手を動かす必要がなくなったのだ。しかし今までの疲れを癒すようにぐっすりと眠りこけた白雪姫に自身を同化させたのだろう。小人たちは何者か邪悪な存在に家が支配されていることに気づく。そして、白雪姫を起こしにいくが、その姿がいたいけな少女であることに驚嘆する。ウォルト・ディズニー氏が自らの実力・成功と若さのギャップに戸惑っていることの反映が見られる。
そして、姫は小人たちにせがまれ、自らの恋愛を赤裸々に、メロディーに乗せながら語らい始める。小人たちは異世界の物語をうっとりと聞いている。新たな文化が野蛮な土地に持ち込まれたのだ。そして、白雪姫はあろうことか、他人の家であるにも関わらず、自分は2階のベッドのある部屋へ眠りにいく。ベッドを奪われた小人たちは、床や鍋の中やタンスの引き出しの中で眠る。あくまでも自分の利益を追求し、手放すことをよしとしない、姫の傲慢な性格が見て取れる。翌日、小人たちは仕事に出かける。姫は、ちゃっかりとその家の主婦にでもなったかのように小人たちを見送る。見送りの際に、全ての小人たちの額にキスをする。ソーシャル・ディスタンスが叫ばれている世の中であるが、これほどの「密」をアニメーションの中とはいえ許していいのだろうか?いや、これは許してはいけないと思う。我々は距離感を間違えているようなちぐはぐな印象を与えられるのだ。そもそも、多数の初老の男たち(全員が髪の毛を全く失っていることから推定60歳は超えていると思われる)に額とはいえ接吻するなど、破廉恥の極みである。誰もこの乱交的行為を子供たちに見せるべきではないと僕は思う。おかげで、感受性の高い幼少の僕は髪の薄い男性に憧れを抱くようにすらなってしまった。ジャン・リュック・ゴダール、ウディ・アレン、ビル・マーレイ……僕のヒーローたちは揃いも揃って薄毛である。
その後、魔女=義母が白雪姫を殺しにやってくる。毒林檎を食べさせて、姫は永遠の眠りに落ちる。小人たちは魔女=義母を追い詰めて殺してしまう。支配者亡き後も、彼らの忠誠心は潰えることはなかったのだ。そして、最後、白馬に乗った王子が白雪姫に接吻をして、白雪姫は生き返る。彼らは幸せに暮らした。ジ・エンドである。
以上が、『白雪姫』のストーリーである。ここまで読んでいただければ、姫がいかに「姫」たるか、いかに権力者=資本家的存在であるかが、見て取れたと思う。DVDの特典としてい付いていた解説付き映像を見ると、それがより、確信へと変わる。ウォルト・ディズニーは、自身が尊敬するチャールズ・チャップリンに帳簿を見せられて、こう言われた。「これ以上言い値を下げてはならない、配給会社はいつだって搾取する」帳面にはとてつもない金額が載っていたという。資本主義者は資本主義者を倒すことによってしか生まれないのだ。そして、『白雪姫』は、自分より上の地位である魔女=義母=クイーンを殺すことにより成り上がる、サクセス・ストーリーなのである。
(8月25日の日記が長くなってしまったので水曜、木曜は休みとする。)
続く
前回までの日記
執筆者:Naoya Takakuwa / ナオヤ・タカクワ
1992年生まれ、石川県出身。東京を拠点に活動するミュージシャン、作曲家。前身バンド、 Batman Winksとしての活動を経て、2017年、 ソロ名義での活動を開始。2018年にアルバムLP『Prologue』をde.ta.ri.o.ra.tionより発表。現在は即興演奏を中心に活動中。2019年には葛飾北斎からインスパイアされた即興ジャズ7曲入りCDーR『印象 / Impression』付きの書籍『バナナ・コーストで何が釣れるか』がDeterio Liberより刊行された。