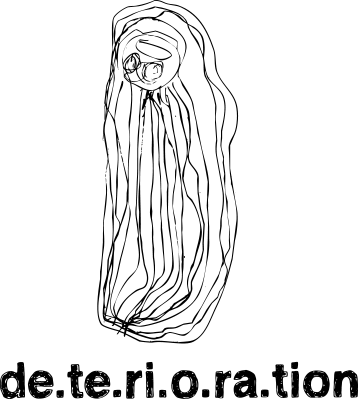MAGAZINE
「BICライターの見せない哲学」音楽家ナオヤ・タカクワによる日常の批評的分析〜第三回
愛煙家としては、必ずそばに置いておきたいのがBIC社のライター。煙草に火をつけるとき、約7割の人間がBICを使う。残りの3割の人間は変わり者である。今にも潰れてしまいそうな喫茶店で手に入れたマッチ、もしくは偶に前髪を燃やしてしまうターボ・ライター、更なる変人は火打ち石と藁を使って火起こしをしてから火をつけるため、煙草を吸おうと思ってから吸い始めるまでに小一時間かかる。少なくともこれらの奇人・変人・スピリチュアリスト達を除いて、殆どの人間はBICを使っているのだ。
ところで、僕は現在禁煙を始めてから4時間が経過したところである。禁煙することにしたのは月に1万5千円分の節約となることが起因している。僕はこの1万5千円分を貯金することにより、払い損ねた年金を支払う助けになると思ったし、そうすれば少しは生きやすくなる気がしていたのだ。しかしながら禁煙のストレスにより、アマゾンで既に1万円分の買い物をしてしまったため、夢は潰えた。結局のところ、禁煙しようがしまいが、手元に残るお金はそれほど変わらないのだ。禁煙した場合にはお金の代わりに不必要なガラクタが増えていくし、喫煙し続けた場合には肺疾患が残るという違いだけだ。どちらの方が幸運かと聞かれれば、個人的にはどちらにもそう大きな違いはないとしか言えない。
僕が言いたかったのは、禁煙中に煙草について書くことの難しさとそのストレスの大きさである。何かをやめようと思っているときに、その「何か」について考えるということは地獄に等しい。それでも僕はやはりこの地獄の中で腰を据えてたった一人で戦うことを選んだのである。何故かというならば、そもそも煙草を吸う理由は、自らの肺を痛めつけ健康を害しているという背徳感や嫌煙主義が蔓延する2020年代において、あえて醜悪な煙を吸いこみ汚臭を放つことを楽しむマゾヒズムにこそあるのであり、それは「煙草を吸わない」という行為によっても同じように得られるものであることに気づいたから、また禁煙中に煙草についての文章を書くことがその快楽を更に高めてくれる小道具として機能することにもまた気づいてしまったからである。
BICの話に戻ろう。BICと他の使い捨てライターの違いは「中身が見えるか、見えないか」である。BICの特徴としては美しい発色のカラー展開であり、人々は自分のキャラクター、または理想像に合わせてカラーリングを楽しむ。大人を演出するブラックや、ユーモアを感じさせるイエロー、可愛らしいピンク、クールなブルー、これもまた可愛らしいパステルカラーの水色など。それらの美しい発色のために犠牲となったのが、中身のオイル残量を目視する機能である。BIC以外のほとんどの使い捨てライターはその筐体が透けており、中身のオイル残量が一目でわかるが、BICはその便利機能を捨て去ることによってライター界の標準としての地位を獲得している。
そもそもBIC社が最初に開発したのはライターではなくボールペンである。最もポピュラーであると思われる「ビック・オレンジ」はやはり胴部分があの特徴的な濃いオレンジ色で塗られているため、中身のインク残量が全く見えなくなっている。そのライター、ボールペンに共に特徴的である「中身が見えない」という特徴だが、BIC社立ち上げ当初はそうでもなかった。以下BIC JAPANの公式ホームページより抜粋。
――1945年、マルセル・ビックはエドゥワール・ビュッファールとともに筆記具会社、BICをフランスに設立、共同経営をスタートさせます。1888年にアメリカにてジョン=J.ルードによって発明されたボールペンは、ハンガリー人のラディスラス・ピロに引き継がれました。ボールペンに多大な可能性を予見したビックは、ピロの特許を買い取り、改良を続け、世界初の使い切りボールペン【ビック・クリスタル】を発売しました。
“信頼できるボールペンを低価格で”をキャッチフレーズに急速にBICブランドが浸透しました。その後、1961年には今日でもベストセラーであり続けるボールペン【ビック・オレンジ】が登場します。1970年には多色ボールペンが誕生しました。今ではBICはシェーバー、ライターをはじめ、さまざまな商品を取り揃えるようになりました――
参照元ーhttp://www.bic-japan.co.jp/history/
マルセル・ビックが最初に作ったボールペンは中身のインクが透けて見える「ビック・クリスタル」であり、「ビック・オレンジ」ではなかった。つまり彼が行ったのは「見える構造」から「あえて見せない構造」への切り替えであり、その見せない哲学はBIC社の様々な他製品――ライターなどにも受け継がれていくことになる。不思議なのが、中身が見えることが長所であり特徴であった「ビック・クリスタル」の利点を捨て去り「ビック・オレンジ」を発売するに至った経緯である。「ビック・クリスタル」の発売が1950年であり、「ビック・オレンジ」の発売が1961年。この10年と少しの間にフランスで確実に何かが起こったのである。
アルベール・カミュは1942年に『異邦人』、1947年に『ペスト』を出版している。ジャン=ポール・サルトルは1943年に『存在と無』を出版しており、実存主義が席巻した時代、それが1950年。それに1952年に起きたカミュ=サルトル論争への準備が行われていた年でもあった。この時代に中身の見えるボールペンを発売することは、「中身=実存」を見せることを表象しているように思える。透明なペン軸の中に見えている黒い液体は、無形的な自意識そのもののようである。また、ペンを使って文字を書く行為は、その時に初めて、自意識を垂れ流す行為となった。
その後、カミュが交通事故によって1960年に一つの生命としての死を迎えた翌年に発売されたのが「ビック・オレンジ」であった。それが意味しているのはカミュの死というより、サルトル、すなわち実存主義の死を予見しているように思える。1962年にはクロード・レヴィ=ストロースによる『野生の思考』が発刊される。この書物による批判から、サルトルの実存主義は実質的な死を迎える。
そして「ビック・オレンジ」が提示したのは中身のインクを隠す行為だ。我々が何かを隠す時、それは隠す対象が恥ずべきものであるからである。アダムとイヴは知識を得る果実を食べ、自意識が芽生えたあとで自身の性器を隠した。性器がなぜ恥ずべき部分であるのか。それが性別を象徴しているからかもしれないし、排泄を意味するものであるからかもしれない。しかしその部分が人間にとって最もプライベートな部分であるということに変わりはない。そもそも「中身」とは「外側」が存在するときにしか存在し得ない。我々の性器は下着の発明以前は「中身」ですらなく、「外側」の一部分であったのだ。
BIC社は時代の流れと共に、インクやオイルを隠した。それが恥ずべきものであるかのように。それによって僕らは見たくないものを見なくて済むようにはなったのかもしれない。少なくとも、残り少なくなったインクやオイルを見て、代わりを買わなければというストレスに煩わされることはなくなった。しかしながら現在我々が戦わなければいけないのは、目の前に転がった無数のライターの中から火が付くものを探し当てることであり、それを一発で探し当てることは天文学的な確率で不可能に近い。本質的なもの=インクやオイルを排泄物=恥ずべきものとして隠したり、逆に見せびらかしたりする文化は60年代から連綿と続いている。我々の中身を隠す場所はインターネットのプロフィールの一部となり、あるものはアカウントに鍵をかけるし、あるものは大量のフォロワーたちに透明性を持って中身を見せびらかしている。だけど我々の本質とはそもそも何だったか。僕らはもしかしたらマトリョーシカ人形のように薄い外側を何重にも重ね着しているのかもしれない。その皮はどこまで剥けばいいのかもはや誰にもわからないし、剥き続けるうちに玉ねぎのように芯の部分しか無くなっていたということになってしまうかもしれない。
でも僕は禁煙を始めたし、どのライターがついて、どのライターがつかないのか把握する必要も無くなった。だってライター自体がもう必要ないからだ。
前回のコラム
執筆者:Naoya Takakuwa / ナオヤ・タカクワ
1992年生まれ、石川県出身。東京を拠点に活動するミュージシャン、作曲家。前身バンド、 Batman Winksとしての活動を経て、2017年、 ソロ名義での活動を開始。2018年にアルバムLP『Prologue』をde.ta.ri.o.ra.tionより発表。現在は即興演奏を中心に活動中。2019年には葛飾北斎からインスパイアされた即興ジャズ7曲入りCDーR『印象 / Impression』付きの書籍『バナナ・コーストで何が釣れるか』がDeterio Liberより刊行された。