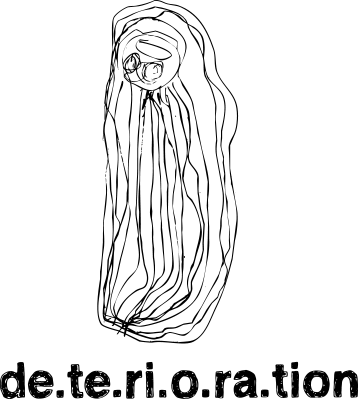MAGAZINE
「ねじを巻く」音楽家ナオヤ・タカクワによる日常の批評的分析〜第八回
ここのところ、一週間か二週間に一度図書館へ行き、三、四冊の本を借りて読む、という生活を繰り返している。生活のための仕事以外の労力のほとんどは本を読むことに費やされ、ほとんどギターを弾くこともなくなってしまったし、映画を観ることもやめてしまった。本はどのように書かれるのか。筆者は何を考えながら、何のために、そしてどうやって文章を書いているのか解読するのが現在のライフワークだ。
僕には極端に何かに傾倒してしまう癖があり、何かに入れ込んでいる間には他の何かは全く手につかなくなってしまう。その対象は少し前にはコーヒーのハンドドリップであったし、その前には鶏もも肉を如何に焼くかであったし、その前にはフランス現代思想であったし、その前にはゴダールの映画であったし、その前にはジャズ・ギターであったりした。これらのことをそれぞれ完璧にマスターする次元まで続けられていたなら、僕は様々な分野において多くの知識を持ち、権威を持つことすらできただろう。
しかしながら、決して僕が何かをマスターしたり、十分な知識を得たり、それを何かに役立てたり、仕事にしたりできることはなかった。ある種の好奇心に突き動かされ「何か」に対して猛烈に突進していくが、ある程度の量の知識が蓄えられ、好奇心が満たされると、僕はその探究を続けることができなくなり、次の物事へと移って行った。おかげで、十数年続けながらも僕のギターの腕は全くと言っていいほど上達していないし、これまでに得た知識は浅いところで留まってしまい仕事へ活かすこともできていない。
この傾向は僕の人生を惨めに支配していて、いつまでも分岐点に立ち止まっているような気分にさせるのだ。目の前に五本の道が並んでいて、そのうちのひとつを選んで進んだとする。途中で自分の進んでいる道が間違いだったのではないかと不安になり、元来た道を引き返す。再び別の道に足を踏み入れるが、やはり進んでいく途中で不安になり、引き返してきてしまう……といった具合に、永遠にゴールや出口のようなものを見ることがなく、行っては戻ってくることの繰り返しでしかない。それは、投げたブーメランの描く軌道に似ているし、やまびこにも似ているし、卓球にも似ているし、犬とやるフリスビー遊びにも似ている。
投げたものが戻ってきたときに感じる安心感であり、快感というものは確かに存在しており、その快楽を、実は我々人間は0歳児の時から知っている。その原初的なものの代表的な遊びが「いないいないばあ」であり、顔が隠れる不安とまた顔が戻ってきたという安心感は、幼児にも快楽を与える。
いろんなものを僕たちは投げるし、そのうちの半分は戻ってこなかったりもする。意図せぬタイミングで偶然、昔投げた品物に出会うこともある。そうした時の感動はより一層深かったりもする。
僕は前述したように、しばらくの間ギターを弾くことをやめていた。本や文章に隠された秘密のようなものを暴くまではギターを手にしないとすら誓いもした。しかしながら、ある日予期せぬギターとの出会いが訪れた。僕は新しいギターを購入することになった。二万円ほどのミニギターで、ナイロン弦の貼ってあるものだ。一応これは「クラシック・ギター」と呼ばれる種類のギターである。ある日急にクラシック・ギターに惹かれるようになってしまった。それがなぜだかはわからない。その流れはあまりに急にやってきたし、特にクラシック・ギターによる演奏を聴いていたわけでもない。ただある日天啓のように、小さなクラシック・ギターを買うという思想がやってきた。
僕はその日の仕事終わりに渋谷にある楽器屋へ向かった。その店は、コロナの影響で営業時間が短縮しており、僕が店にたどり着いたのは閉店間際のことだった。僕は二種類のギターを試奏させてもらった。店員は、閉店間際にも関わらず、たっぷりとその二本を快く試奏させてくれた。ギターを弾くのは一か月ぶり、いやもしかしたらもっとだったかもしれない。とにかくその試奏の瞬間、脳天に稲妻が直撃するような快楽が訪れた。自分の指がナイロンの弦と一体となり、僕自身の体をも振動させていた。まるでギターの音色は僕自身から響いているようだった。雨の中、僕はそのギターを担いで帰った。さまざまなギターにまつわる記憶が頭の中を蠢いていた。
僕は「帰ってきたのだ」と思った。ギターは僕の帰る場所、家であり、そこから一時離れはしたが、帰ってきた。帰る場所のある安心感というのはもちろん誰もが知っていることだ。一か月かそこら、と言っても僕とギターとの関係においては随分長い時間であったのだ。
そして僕は現在、ギターを弾かないという誓いを破り、毎日『マイ・フェイヴァリット・シングス』を練習したりしている。この新しいギターは、チューニングの精度が甘く、部屋の暖房をつけただけで半音ずれる。僕は暖房をつけるたびにチューニングを直すし、暖房を切るたびにまたチューニングを直す。ぎりぎり、と少しずつ「ねじ」を巻いてやる。このギターは半音だけ進んだり、半音だけ下がったりするので、僕が元の位置に戻してやるという役目を負わされているのだ。何かを元に戻すという行為は自分が元の場所に戻ってくるのとは違う役割を演じることである。
例えば、フリスビーを運んでくる犬の役割、卓球の相手の役割、やまびこにおいての山の役割、いないいないばあをする叔母さんの役割。誰かが「ねじ」を巻いてやる。はいはいする赤ん坊をベッドに戻してやる。ホールデン・コールフィールドはライ麦畑の子供たちをキャッチしようとした。僕らは何をキャッチしてやるべきなのか。それともキャッチされる側であるのか。
僕らは随分遠くまできてしまったように思える。生活は変わり、人付き合いも変わり、仕事のやり方も変わり、考え方も変わった。実家には二年帰っていないが、たまにテレビ電話をするおかげで、以前よりはっきりと家族の顔を思い出すことができる。これはある意味ではプラスの変化かもしれない。しかしテレビ電話で存在するのは視覚と聴覚に訴える情報だけであり、他の五感――「触覚」「味覚」「嗅覚」の機能は相手を感知するために使われない。
元の世界に戻った時(戻ることがあったとして)そこには深い感動と安心感と快楽があるかもしれない。もしくはあまりに久しぶりなのでうまく馴染むことができないかもしれない。同窓会で会った学生時代の友人と何を喋っていいかわからなくなる瞬間のように。それが他人のようにすら感じるかもしれない。そうならないためには、今引きかえす必要があるのではないかと思う。もしくは、「ねじ」を巻く。もしくはキャッチして元のところに戻してやる。そうした作業は自分があちこちへ行くよりも、ずっと能動的で、利他的なものである。僕はそういった作業をできるようになれればな、と思う。しかし、それは勿論無理やり外を出歩くとかマスクをしないとかそういったことではない。もっと理性的で秩序だったやり方が必要なのだ。死ぬための「ねじ」ではなく、生きるための「ねじ」を緩やかに巻くことができればと、僕は思っているのである。
前回のコラム
執筆者:Naoya Takakuwa / ナオヤ・タカクワ
1992年生まれ、石川県出身。東京を拠点に活動するミュージシャン、作曲家。前身バンド、 Batman Winksとしての活動を経て、2017年、 ソロ名義での活動を開始。2018年にアルバムLP『Prologue』をde.ta.ri.o.ra.tionより発表。現在は即興演奏を中心に活動中。2019年には葛飾北斎からインスパイアされた即興ジャズ7曲入りCDーR『印象 / Impression』付きの書籍『バナナ・コーストで何が釣れるか』がDeterio Liberより刊行された。