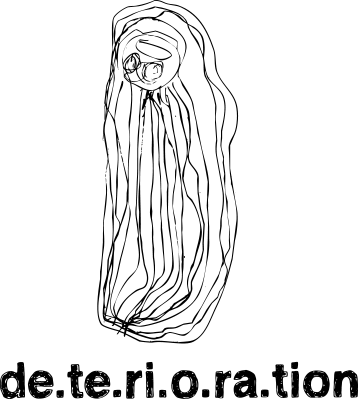MAGAZINE
「ウディ・アレンはお好き?〜『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』とセレーナ・ゴメスについての考察〜」音楽家ナオヤ・タカクワによる日常の批評的分析〜第十一回
ウディ・アレンの『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』を観た。僕がこの映画をみるのは四回目だ。一回目は席数を半分に減らした映画館で、後の三回はネットフリックスで観ている。一応断っておきたいが、僕が何度も同じ映画を観るというのはまれなことだ。同じ映画を絶対に四回は観るという性癖を持っているわけではない。それでも、ウディ・アレンの映画は何度も見ることがある。一番見たのは『アニー・ホール』だろう。『アニー・ホール』は全盛期のダイアン・キートンと全盛期のウディ・アレンが融合して核爆発を起こしたような映画であり、何度見ても最初に見たのと同じ感動を味わえる。
とはいえ、最近のウディ・アレンを何度も観ることはまれだ。僕はウディ・アレンの全盛期は七十年代だと思っているし、ウディ・アレンのノスタルジーと諧謔は二十一世紀にはそぐわないし、少々そのおかげで痛くなってくる。
『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』もかなり痛い。現代を舞台にしながらも、主人公はポーカーゲームで小金を稼いでいるし、登場人物が全員レトロ趣味な服装をしているし、主人公が紙煙草にパイプをつけて吸っている。それらを微笑んで見られるのは、ウディ・アレンの作品だからだろう。
僕が何故こんなに何度もこの映画を観ることになったのかといえば、ネットフリックスで観られるからだろう。ネットフリックスで観られるウディ・アレンの作品はこれと『ミッドナイト・イン・パリ』だけだし、『ミッドナイト・イン・パリ』は既に十回ほど見ているからだ。ネットフリックスで見られるまともな作品は限られている。とはいえ、とんでもない作品がいくつもあるというのも事実だろう。デヴィッド・リンチの『ジャックは一体何をした?』は名作である。デヴィッド・リンチが猿を一七分間尋問するというだけの映像だ。
話が逸れたが、『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』には主要人物が何人かいる。その中でもセレーナ・ゴメスの演技はかなり不気味だ。他の役者は真面目に演技をしているように思えるが、ゴメスの演技は素人が間違って映画に出てしまったという印象さえ受ける。この不自然さの原因を究明するため、何度かゴメスの登場シーンを巻き戻して見てみた。最初は彼女の平板なヴォイス・トーンにそれがあるのではないかと思った。倍音の極端に少ない安物のバスクラリネットのような声で彼女は喋るし、その音程は常に下の方に留まっている。
しかし何度も見返していくうちにそれだけが原因ではないことがわかる。彼女がセリフを口にする時、他の出演者がしゃべり終える0.1秒前に喋り始めているのだ。もちろん演出上そのようなアプローチが取られることは珍しくないが、彼女の間の取り方というか間の取れなさはそういうノーマルな間の取れなさとは一線を画している。彼女の表情もほとんど変化しない。
恋に落ちたようなシーンでも真顔のままである。ゴメスが演じるチャンがインディー映画に出演していて、演出上ティモシー・シャラメとキスをするシーンがある。ゴメスはこの手の撮影に慣れている雰囲気で、シャラメは演技には素人といった役柄である。このシーンでゴメスはシャラメに、そんなキスのしかたはない、といったようなことを説教する。しかし実際にはゴメスの表情が終始固いままであり、演技が下手であるという、両者の演技能力が設定と実際とで逆転しているという現象が起こる。
この逆転現象は演技と現実との差異を感じさせる違和感として残る。その違和感は不気味である。映画のストーリーへの没入を損ない、映画を見ながらにして、映画の撮影裏を想起させるものだ。これは新スタイルの演出だとも言える。この逆転現象により、エル・ファニングが精一杯の演技をしているのが、メタ的に認識できるようになる。僕たちは映画を見ながらにして、映画内と映画外を行き来する。
夢と現実の対比が映画内で行われる例はこれまでにもあった。例えば、ウディ・アレンの『カイロの紫のバラ』がそうである。ミア・ファロー演じる主人公が、映画内に出てくる映画を見てその主人公に恋をする。すると、その主人公が映画の中から現実に文字通り飛び出してくるという演出だ。この中では『カイロの紫のバラ』という映画の中で、別の映画が走っていて、その映画と『カイロの紫のバラ』のストーリーが入り混じるというふうになっている。それは映画の中で二種類の認識が生まれるということだ。
『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』の場合はそうではない。僕らはあくまで一つの作品の一つのストーリーを追いながらにして、楽屋裏を覗き見るような気分になる。それは『カイロの紫のバラ』のようなオールドスクールな二段階演出とは全く違うし、ドキュメンタリー映画などとも違う、新感覚の演出だ。
シャラメ演じる主人公ギャツビー(ギャツビーってそれ自体がすごい名前である)がラストシーン近く、母親から告げられた出自の秘密も、この二段階性を裏付けている。ギャツビーの母親は自身が元々娼婦であったこと、そして高級なものや洗練されたものを好むのはその出自があるからこそなのだと語る。裕福な暮らしの裏に潜む、自身が娼婦の子だという事実が、リアルとアンリアルが混在したギャツビーの運命と、そして観客にとってのリアルとアンリアルが混在した状態を気づかせる。
シャラメはエル・ファニングを諦め、セレーナ・ゴメスをとる。エル・ファニングの演技は過剰だ。演技も過剰だし、彼女が演じるアシュレーの天然ぶりも過剰である。緊張するとしゃっくりが出るという症状、ウディ・アレンとダイアン・キートンをミックスして憑依させたような喋り方。その過剰さはアンリアルであり、《夢》そのものだということもできる。実際、映画の中でファニングは夢を見ているのではないかとさえ思う。憧れの監督へのインタヴュー、憧れの俳優との情事、杯数が重なる酒、マリファナ、非現実性へとどんどん向かっていくのがファニング演じるアシュレーなのだ。セレーナ・ゴメスの演技が逆説的に映画というアンリアルなストーリーに対しての、楽屋裏もしくは私生活というリアルを想起させるのと対照的な形になっている。
シャラメが選び取ったのはゴメスという現実であり、それは監督アレン氏の意志のようにも思える。そもそもシャラメのキャラクターは冒頭で述べたように、現代において非常にアンリアルだ。ポーカーゲームで小金を稼いでいるし、レトロ趣味な服装をしているし、紙煙草にパイプをつけて吸っている。ギャツビーというキャラクターは大学を辞めて、ニューヨークに残るという。それは構図的には現実を捨てて、夢の中に生きる、という意味にももちろん安易に捉えることは可能だろう。
しかし、ニューヨークという自分が生まれた土地に戻ること、母親そして自身の出自と向き合うこと、またゴメス演じるチャンが以前の恋人の妹であること。それらは、自分自身の過去と向き合うということを意味している。過去は徹底的にリアルだ。現在と未来は予測することが不可能だが、過去だけは決して変わることがないのだ。それらはウディ・アレン自身のレトロ趣味を肯定しているようにも思えるし、少年へと戻ろうとしているようにも思える。彼の配偶者を見れば、彼が少年に戻りたがっていることは容易にわかる。実際、チャンという名前がアジア系を想起させる名前じゃないか。ウディ・アレンは、自分が夢見がちな態度をとっているわけではなく、《過去》こそが現存するリアルの全てなのだと訴えかけたかったのじゃないか?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
まあ、そんな考え方もあるよなと思いながら、夢想家である僕自身はウディ・アレンとは真逆であり、過去を全て洗い流したい方の人間だなと思う。いつまでもまとわりついてくる過去という奴はいくら振り払ったって常に隣にいるんだ。新しい人間になろうと思ったっていつでも奴らが手を伸ばして足首を掴みかかってくる。なんでそんな彼とは真逆の僕という人間がウディ・アレンに惹かれてしまうのかよくわからない。だけど一つ言えるのは彼が過去を堂々と見せびらかすことに安心感を覚えるってことだ。『アニー・ホール』だってそうだった。ウディ・アレンとダイアン・キートンが破局するまでのことを、本人たちが演じているのだからすごい。
もう一つ、一番すごいのは『レイニーデイ(以下略)』でフランク・シナトラの歌った曲をティモシー・シャラメが歌っていることだ。ウディ・アレンはフランク・シナトラとは過去に確執があった……はず、ミア・ファロー関連で。
それらを見て、感動し、憧れる、ということは、僕だって過去を堂々と受け入れたり、曝け出したいんだろう。まだ、そこまでは達していないけれど。
ま、とにかく僕らはみんなゴメスにやられちまったという他ない。
前回のコラム
執筆者:Naoya Takakuwa / ナオヤ・タカクワ
1992年生まれ、石川県出身。東京を拠点に活動するミュージシャン、作曲家。前身バンド、 Batman Winksとしての活動を経て、2017年、 ソロ名義での活動を開始。2018年にアルバムLP『Prologue』をde.ta.ri.o.ra.tionより発表。現在は即興演奏を中心に活動中。2019年には葛飾北斎からインスパイアされた即興ジャズ7曲入りCDーR『印象 / Impression』付きの書籍『バナナ・コーストで何が釣れるか』がDeterio Liberより刊行された。